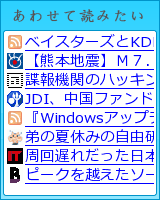10周年過ぎてしまいました…
前回のブログで2月21日の10周年記念日にブログを更新する予告をしていましたが、恥ずかしながら、完全に失念してしまいました( ;∀;)
加齢による記憶の衰えを改めて自覚した次第です。
本来、2月21日に、これまでの振り返りとこれからのことを考えてたくさん書こうと思っていたのですが、もはや、やる気もなくなってしまいました。これは、小学生が「8時から勉強するぞ」とやる気になるのと似ているかもしれません。8時を過ぎてしまったら、もういいかと思ってしまい、次は「9時から勉強するぞ」というように、キリのよい時間から頑張ろうという心境ですね。そうなると、10周年の次にキリのよい年は15周年とか20周年になってしまいますので、随分先の話になってしまいそうです。
ということで、少しだけ振り返ろうと思います。
10年前の平成24年2月21日から正式に恵比寿駅前の住居兼事務所の賃貸物件(ドエリング恵比寿というマンション)において琥珀法律事務所をスタートさせました。そのときは、確か15坪くらいしかスペースがなく、相談室1つと執務スペースを確保するだけでいっぱいいっぱいでした。当時、広尾にあるおしゃれなオフィス型ビルを賃貸したいという思いもあったのですが、そこの家賃は1,5倍の価格だった上に、保証金も6か月分おさめなければならなかったため、経済的な事情から恵比寿にある上記物件を選びました。恵比寿の同物件は住居兼事務所タイプだったため、保証金は不要だったので、初期投資額が安くすんだのです。また、駅から徒歩1分という恵まれた立地だったことも選んだ理由の一つでした。
開業当初、相談者が来てくれるのか、問い合わせはあるのか、果たして食べていけるのか、といろいろ不安でしたが、当時はまだ今ほど法律事務所間の競争は激しくなかったので、インターネット広告によって、それなりに問い合わせはありました。主に労働事件と刑事事件を中心に広告していたのですが、これまでに経験したことのない事項に関する相談も一定数あり、その都度、調べて対応するように努力しました。この過程で自身の実力が延びていっているはずだと思えば、時間がかかっても調べることは苦ではありませんでした。
当時、とにかく、事務所経営を安定させたいという思いから、基本的に依頼されれば断らずに受けるというスタンス(ただし、要求が正当でないもの、証拠が皆無のものはさすがに受任しませんでしたし、予想される経済的利益が少なく、弁護士に依頼すると経済的にマイナスになってしまうものもお断りしていました。)で対応した結果、業務過多でしばしば徹夜を余儀なくされ、一番働いた時期だったように思います。恵比寿駅前にあるモンベルという登山用品店で寝袋とマットレスを購入したのはいい思い出です(笑)。
30代前半だったから無理できたのかもしれませんが、41歳になった今、同じくらい働けと言われてもほぼ不可能だと思いますし、あの頃のように働きたくもありません。ただ、あの頃に精一杯働いたおかげで、それなりに経験を積んで知識も得られ、今につながっていると思われ、その意味では、多少無理しても働いてよかった、働いた意味はあったと考えています。年を重ねてからでは、体力も気力もどうしても衰えてしまっていますので(実際、年々、健康診断でひっかかる項目が多くなっています。)、苦労するなら若いときの方がよいでしょうしね。また、一定期間精一杯働いたことは自分にとって自信となっており、多少の苦労も少しは余裕を持って対応できるようになったと思います。
もちろん、今でも知識や経験は十分ではありませんので、今後も努力を重ねていくつもりです。幸いなことに、私は基本書を読んだり判例を調べて読むことがけっこう好きなので、全く苦に感じません。この点はロースクール生だったときから飛躍的に私が進歩した点だと思います(笑)。
振り返ると、独立した当初は、今ほどの規模にまで琥珀法律事務所を拡大できるとは夢にも思っていませんでした。せいぜい、弁護士数人、事務員数人の共同経営形態しか念頭にありませんでした。広いオフィスに引っ越せるとは思っていませんでしたし、全国各地に支店を展開できるとも思っていませんでした。拡大できたのは縁があって多くの人から仕事をいただけるようになったからであり、依頼してくださった方々や顧問先となってくださった方々、私の相談に乗って支えてくださった方々に深く感謝しています。また、縁あって琥珀法律事務所に入所して働いてくれている方々にも同様に感謝しています。
今後も相談者・依頼者の方々のお役に立てるように、より良いリーガルサービスの提供を目指して頑張っていきたいと思いますし、内部的には、気持ちよく働ける環境を整えるように努力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2022年2月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
10周年??
今日は、2022年2月12日。私の記憶だと、事務所を開設した日は2012年2月12日だったと思うので、琥珀法律事務所は今日でとうとう10周年を迎えたんだと思って感慨にふけっていました。
そして、10周年の記念日なので、この10年間を振り返ってブログを更新しようと思い、珍しく早朝から事務所に出勤し、満を持して、パソコンを立ち上げた次第です。昨日から、どんなことを書こうかといろいろ考えていました。
で、ふと、「事務所を開設した日にはブログを書いているはずだ」と思い、過去に書いたブログをさかのぼって探してみました。ところが、2012年2月12日に更新された記録がない。それどころか、2012年2月15日のブログには「開業まであと1週間を切りました」と書いてある…。………??
もしかするとと思って、続けてブログを見てみると、なんと、開業日は2012年2月21日でしたΣ(・□・;)
人の記憶はあてにならず、思い込みって怖いものですね。なぜか「絶対に2月12日だ」と思い込んでいたので、自分でも驚いています。記憶は案外あてにならないことを自覚させられました。日々の裁判に生かせそうな経験です。
周囲の何人かには「12日で10周年なんです~」と言っていたことが恥ずかしい。今さら、わざわざ電話して「実は間違ってまして、正確には2月21日です」なんて訂正しても、先方にとっては(おそらく)どうでもいい話なので、このブログを見てくれることを期待するにとどめます。
ということで、次の21日こそ、過去を振り返ってちゃんと書こうと思います。
2022年2月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
ファイナンシャルプランナー
今年に入ってから高頻度に更新しています。年始のロケットスタートであり、来月からまた更新頻度は下がっていくと思いますが、今年もせめて月に1回以上は更新していきたいと思います。
さて、本日の午前中から午後にかけて、ファイナンシャルプランナー(FP)3級試験が行われまして、実は私も受けてまいりました。
「ファイナンシャルプランナーってなんとなく役に立ちそう」と軽く考えて受験を決意し、テキストを買ってはみたものの、ずっと開くことなく直前までそのまま置いていたので、なかなかしんどかったです。
ただ、午前中の学科試験の択一の半分は〇✖問題で2択なので、けっこうなんとかなりました。また、午後の実技試験(計算問題)については、苦手意識があったのですが、回答時間が十分にあったので、こちらもゆっくり考えて回答できたと思います。あと、宅建の勉強をしたことがあったのですが、その知識がけっこう役に立ちました。
FP2級または3級を取得のためにする勉強は、とても有益だとと思います。保険や税務、株式の基本的な知識を身につけるのに役立ちますので、法律事務所の事務・弁護士に取得を勧めたいと思います。自身のライフサイクルを見直すきっかけにもなりますし。
とはいえ、新人の方については、事務所に入所してからしばらくの間は、仕事を覚えるのに大変で勉強する時間的な余裕があまりないと思いますので、余裕のある修習中に思い切って勉強するのがいいんじゃないかという気がします。
そういえば、私が修習生だったときは、修習同期で簿記3級を受けようという話になったのですが、全く勉強せずにいて、試験そのものを受けなかったことを思い出しました(何人かはちゃんと勉強していて、そのまま受けて合格していました。)。今思えば、敵前逃亡みたいなもので我ながらカッコ悪かったなと後悔しています。ということで、興味のある修習生は是非、FP試験にチャレンジしてみてください。
2022年1月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
労働法関連書籍の改訂が目白押しです
再び、コロナ感染者数が急激に増大しつつありますね。一体いつになれば落ち着くのかと思いますが、ここが踏ん張りどころなんでしょう。
さて、これまでにこのブログで、令和3年版労働基準法の上巻と下巻、リーガル・プログレッシブシリーズの労働関係訴訟ⅠとⅡが改訂され、いずれも労働問題を取り扱う弁護士にとって有用とお伝えしました。
そんな中、日本労働問題弁護団編著の「新・労働相談実践マニュアル」が発売されました。この書籍はかなり前に発売されて改訂を繰り返しているものでして、とても信頼性のある書籍です。そういえば、私が弁護士になって間がないときに、改訂前のものを購入し、労働事件を解決するにあたって何度も目を通した思い出があります。この本と日本労働問題弁護団編著の「労働審判実践マニュアル」、菅野和夫先生の「労働法」(弘文堂)でなんとかやれていたといっても過言ではありません。
日本労働問題弁護団編著の上記書籍は、東京では裁判所の地下の書店や弁護士会館の地下の書店で売られていますが、それ以外の都道府県ではなかなか見つからないかもしれません。欲しい人は、日本労働問題弁護団のホームページから購入を申し込むとよいと思います。この本も、労働問題を取り扱う弁護士にとって有用です。
それにしても、労働法関係の重要書籍の改訂が相次いでいますね。事務所で購入する場合はさておき、弁護士個人で購入するとなるとけっこうな値段となるので、ちょっと大変かもしれません。同じ事務所の弁護士で買い分けするなどしてもいいかもしれませんね。
2022年1月21日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
労働事件をやるなら買いだと思う。
今年は、昨年に続いて労働事件を扱う実務家にとって重要な本の改訂が目白押しな感があります。
というのも、以前にブログで紹介したリーガル・プログレッシブシリーズの「労働関係訴訟」が久々に改訂されたのに引き続き、同様に実務家が労働事件を取り扱うにあたって指標となる労務行政発行の「労働法コンメンタール」も改訂・発売されたからです。
上記の本の正式名称は「令和3年版 労働基準法 上巻」と「令和3年版 労働基準法 下巻」であり、厚生労働省労働基準局が編集している点で信頼性がとても高いと思います。労働基準法のコンメンタールはほかにも発売されていますが、国(行政)がどういう見解に立っているのかを確認する意味でも有用な書物です。お値段はどちらも税込み約7500円となかなかお高いのですが、滅多に改訂されないので、買っておいて損はないと思います。なお、改訂前のものは「平成22年版 労働基準法」の上下巻でした。実に11年ぶりの改訂なわけです。
労働事件に興味のある修習生や労働事件を取り扱う事務所に入所予定・入所した修習生・新人弁護士の皆さんには強くお勧めしたいと思います。
2022年1月11日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。とうとう2022年が始まりました。
一昨年から続く新型コロナ騒動が未だに落ち着かず、予断を許さない状況にあると思います。昨日のニュースでは、東京をはじめとして、全国的にコロナ感染者数が急増したようですし。もうしばらくの間は、マスクの着用、手指の消毒をはじめとして、気をつけなければいけないですね。
さて、今年も昨年同様、最低1か月に1回はブログを更新するという目標を掲げ、のんびり気ままに好きなことを書いていきたいと思います。
昨年は、いろいろと健康面で悩まされておりまして、病院に行くことが多かった1年でした。やはり、人間、40歳代になると、なにかしらの不調が出てくるものなのかもしれません。ここらで、身体をリセットして休ませるべく、日々の食事や運動に気をつけたいと思います。
そういえば、今年こそ、会食がある日と出張の日、悪天候の日を除いて毎日ジョギングしようと決意し、一昨日から走り始めました。また、軽い筋トレも行うこととし、腕立てとスクワットも一定回数行うようにしました。
すると、本日時点で、なかなかの筋肉痛に悩まされる結果となりました。数年ぶりに運動すると、こうなるのが自然でしょうね。せめて、倒れたバイクを起こせるくらいの筋力を維持したいと思います。
いつまで運動を続けられるのかわかりませんが、身体を動かせるうちに、適度に続けたいと思っています。
それでは、今年もよろしくお願いします。
2022年1月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
ようやく発売された改訂版
前回の更新に続けて、早いペースでの更新です。
さて、今回、私が以前にこのブログで何度かおすすめしたことがあるリーガル・プログレッシブシリーズの1冊である「労働関係訴訟」(青林書院)の改訂版が発売されたので、ちょっと嬉しくなって更新しようと思った次第です。
改訂前のものは、2010年3月に発売されていたので、実に10年半年ぶりの改訂となります。著者の渡辺弘さんは東京地裁労働部の元部長(元裁判官)ですので、上記書籍の信頼性は高いと思います。実際、旧版を読んでいてとても勉強になりましたし、役にも立ちました。
そんな上記書籍が、この度の改訂で、ボリュームをアップして、2分冊となって登場しましたので、労働事件に携わる弁護士(特に新人の弁護士)には以前と同様に強くおすすめしたいと思います。
なお、2,3年おきに改訂されるとなると買い替えに若干躊躇してしまうのですが(ほぼほぼ内容に大差がない改訂もありますので)、今回のように10年ぶりでの大改訂となると気持ちよく買い替えることができますね(笑)。
2021年12月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
侮辱罪で在宅起訴?
ここ最近仕事がなかなか終わらないのですが、今日は久々に深夜まで事務所に残って仕事をしています。
そんな中、ふとインターネットを見ていたら、飛行機内でマスクの着用方法を注意された67歳の男性が注意した女性に向かって「コロナみたいな顔してからに」と言い放ったという事案で、男性が在宅起訴されたというニュースを目にしました。
ニュースによれば、男性は否認しているとのことですので、罪を認めていることを前提になされる略式起訴という手続をとることはできません。したがって、検察としては、不起訴処分とするか起訴するかの二者択一しか選択肢がないことになり、上記の事案では、十分な証拠があって犯罪を立証できる,男性の犯情は悪い(注意を受けたことに逆上して、他人に対して「コロナみたいな顔」って言うのは、無礼すぎますからね。)ということで起訴されたものと考えます。
上記について、侮辱罪で起訴されるのは珍しいなぁと気になって調べてみたら,今年の9月に侮辱罪の法定刑を現行の「拘留・科料」から「1年以下の懲役若しくは禁固又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる刑法改正案が法務大臣に提出されていたことを知りました。上記の在宅起訴の背景にはこの厳罰化の流れも関係しているのかもしれません。
確かに、拘留(30日未満の身柄拘束)と科料(1000円以上1万円未満の財産刑)という刑罰は上限が軽すぎるように思いますので、改正には反対しませんが、個人的には、厳罰化よりも、侮辱行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料の金額を増額した方が侮辱行為を効果的に抑制できるのではないかと思っています。実際には,侮辱されたといって告訴しても,よほどの証拠(録音,録画、目撃者,SNS上のメッセージ等)がない限り,警察は簡単に捜査してくれないと思うからです。
現状,侮辱された場合の慰謝料額は低廉にとどまっておりますので,弁護士に依頼して民事訴訟を提起し、慰謝料の回収を図ろうとしても,弁護士費用の方が慰謝料よりも高くつくことが多いという事情があります。そのため,侮辱を受け,その確たる証拠を有していても,泣き寝入りせざるを得ないという人は相当数おられると思います。慰謝料を高額化すれば,このような泣き寝入りの事態を減らすこと,侮辱行為の抑制につながると思いますが,他方で,表現行為の委縮にもつながりかねないところなので、単純に慰謝料の高額化を図るわけにはいかないのが悩ましいところです。
実際には,侮辱行為に該当するか否かの判断が難しい表現はたくさんありますからね。
こんな風にいろいろ考えてこのブログを書いていたら、時間が思いのほか経過していたので、今日はこのへんにしときます。
2021年12月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
シニア人材という希望
今年も残すところ、あと1か月となりました。ようやくコロナも収束だなと思っていたところに、オミクロン株が新たに発生し、既に日本に上陸している(感染者が出た)というニュースを見て、残念な気持ちになりました。しばらくすると再び、自粛生活に戻らざるを得ないかもしれませんね。
さて、今回、あるご縁で中原千明さん著の「シニア人材という希望」(幻冬舎)という本を読みました。
今後の高齢化社会を見越して、60歳以上の方(シニア人材)を雇用して事業をうまく展開していくにはどうすべきか?という点を中心に、シニア人材の特徴や問題、考え方について切り込んで述べられており、シニア人材の採用のみならず若手人材の採用にあたっても役に立つ知識が書かれています。
著者自身が、シニア人材を積極的に採用して事業を展開しておられるので、その話には相当な説得力があります。
なるほどな~と思いながら読み進めていましたが、ふと、「そういえば弁護士業界には定年ってないよな?」と思い、いろいろと考えました。法律事務所は弁護士1~数名による個人・共同経営のところがたくさんあり、弁護士個々人は個人事業主という立ち位置なので、基本的に「定年」っていうのはないんですよね(弁護士法人所属の弁護士についてはさておきます)。それを喜ばしいこととみるかどうかは人それぞれだと思うのですが、私は、やる気さえあれば、60歳以上になっても働き続けて活躍できるという点も弁護士業の魅力の一つではないかと思いました。
上記の著書にも書いてありましたが、何歳になっても、やりがいのあることをしたいという人は多いはずです。そして、弁護士業は一生懸命取り組めばとてもやりがいを感じることができる仕事ですので、いくつになっても働いて社会に貢献したい、誰かの役に立ちたいという気持ちのある方については、弁護士を目指すというのは有力な選択肢になるのではと思います。
もちろん、年々法律は改正されますし、裁判例も増えていきますので、自己研鑽としての勉強を続けることは不可欠ですが、それを楽しめる方にとっては弁護士は向いている職業だと思います。
さて、私はいつまで弁護士を続けることができるのかわかりませんが、気力と体力が続く限り続けたいですね。
2021年12月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
令和3年度賃貸不動産経営管理士試験
一昨日、国家資格となった賃貸不動産経営管理士の試験が行われました。
弁護士になって以来、これといった資格をとったことのない私ですが、最近、賃貸不動産経営管理士という資格に興味をもち、一昨日の試験を受けてきました。試験勉強を始めたのはわりと直近で余裕がなかったのですが、過去問を見る限り、賃貸借に関する弁護士実務と親和性がある内容でわりと回答できたこと、不動産投資に関する税務やマンションの各種設備の仕組み等が問われる内容で興味深かったことから、勉強は苦痛ではありませんでした。というよりも、内容が有益で生活の役に立ちそうだったので、勉強をそれなりに楽しめました。
勉強しなくても常識で判断すれば回答できる問題(選択肢の内容が明らかに不自然な場合等)が過去問にたくさん出ていたので、焦りつつも、「試験はなんとかなるんじゃないか」と思っていました。
ところが、今年から国家資格化したせいか、本番の試験内容はガラッと傾向がかわっていました。過去問と異なり、特定賃貸借契約や標準賃貸借契約書の内容を問う問題が増え、過去問をメインとして勉強していた私にとっては、なかなか厳しいものでした。今年の問題は「過去問解いていればなんとかなる」というようなものではなかったですね。
過去問を数回解いていてそれなりに自信があったのに、試験終了後は「やばいかな」と焦るくらいでした。また、受験者の出席率がとても高かったことも、「記念受験組は少ないな」という考えにつながり、緊張感を高めました。なお、インターネット上のニュースには受験者数は過去最高の3万2461人、受験率91.3%と書いてあったのですが、この受験率は私の実感と合っています。
で、「落ちたらまた来年受ければいいや」という軽い気持ちで知り合いの先生と一緒に解答速報がインターネット上にアップされるたびに採点し、一喜一憂していました。全く解けなかった場合は別として、実はこの自己採点の瞬間が一番ドキドキして楽しかったりするんですよね。結果として、40点以上は確実にとれていたので(なお、試験50点満点であり、昨年度の合格点は確か35点くらいだったと思います。)、マークミスをしていない限り、合格していると思います(そのように信じたいです)。やはり、知らない問題が出題されてもすぐに諦めないことは大事ですね。
たまに本業以外の勉強をすると、気分をリフレッシュできていいなと今回強く思いました。この調子で引き続き、新たな資格取得を目指して頑張りたいと思います。
2021年11月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記