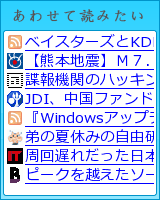令和7年度マンション管理士試験
今年も残すところ20日程度となりました。今年の年末は、金融機関を除いて大型連休が取得可能な感じですね。琥珀法律事務所は、12月26日を最終営業日とし、来年は1月5日月曜日から業務を開始します。
さて、今年もマンション管理士試験を受験してまいりました。最初に買った参考書の発行年が2019年だったので、早6回も受験したということになります。で、今回の結果は…というと、自己採点で32点でして、順調に撃沈しました。おそらく合格予想点は37点以上になると思われ、5点以上足りないということになります。
受験直後の感触では、昨年よりもやや優しくなったように思ったのですが、そもそも、絶対的な準備が足りておらず、知らない問題(単純な暗記問題)を出されるとお手上げでした。
昨年の受験直後の時点では、来年こそ受かるぞと意気込んでいて、最低1か月は準備しよう(勉強しよう)と思っていたのですが、今年の秋ごろにはそんなことを忘れてゴルフの予定を入れすぎてしまい、これに相まって急な仕事の対応もあって、案の定、勉強時間が全く足りませんでした…。
己の自制心のなさ、覚悟のなさを恥ずかしく思いますね…。6回という受験回数は司法試験よりも多いですww いわゆるベテラン受験生の仲間入りという感じですね。
9月~11月はゴルフのオンシーズンですので、ゴルフ好きの私としては、11月末の日曜日という試験日設定は厳しいものがあります。2月とかに日程変更されないかなぁなんて空想にふけってしまいますが、現実は、来年も11月末に実施されるでしょう。いずれにせよ、さすがにもう受かりたいです。
マンション管理士は名称独占資格に過ぎず、独占業務があるわけではありませんので、取得してもしなくてもよい資格(特定の仕事を行うにあたって必須の資格とはいえない)といえ、それゆえに危機感がないのかもしれません。
ただ、いつまでもこの資格の勉強にかかりきりになっている場合ではなく、他の資格に関する勉強も行っていきたいと思っていますので、2026年度のマンション管理士試験に合格することをもって、この分野の勉強をいったんストップしたいと思います。三度目の正直は過ぎてしまっているので、7度目の正直を実現すべく頑張ります。
タグ
2025年12月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
通常逮捕の要件
今月も3分の1を経過しました。今年もあと2か月弱ですが、インフルエンザが世間で流行っていますので、体調管理に気をつけて過ごしていきたいと思います。
さて、昨日、N国党の立花孝志氏が名誉毀損の被疑事実により通常逮捕されたとの報道がありました。この逮捕について、逮捕の必要性があったのかという点が問題として取り上げられており、X等で投稿が繰り返されています。そのため、参考までに、このブログでも簡単に説明しようと思います。
通常逮捕については、刑事訴訟法199条1項本文が「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と定めています。この規定の仕方に照らせば、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」さえあれば、逮捕状の発付を受けて通常逮捕が可能なように読めますね。
しかし、199条1項但し書きは、上記本文について、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく、出頭の求めに応じない場合に限ると定めています。また、199条2項は、裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官等の請求に応じて逮捕状を発すると定める一方で、同条2項但し書きにおいて、「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とも定めています。
上記の条文構造に照らせば、逮捕状の発付にあたっては、逮捕の必要性があることを要件と解することができ、199条1項但し書きが30万円以下の罰金等に当たる軽微な犯罪について、住居不定や任意の呼び出し不出頭を要件としているのは、軽微な犯罪の場合には類型的に逮捕の必要性が認められにくい(小さい)と捉えているためと考えられます。
※ 罰金に処されることをおそれて逃亡を図ったり、証拠隠滅を画策する人は少ないでしょう。
また、刑事訴訟規則142条は、逮捕状の請求書に帰しすべき事項を定めていますが、その記載事項の中には「被疑者の逮捕を必要とする事由」が含まれていますし、同規則143条1項は「逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。」と定めていますので、やはり、逮捕の必要性は逮捕状発付の要件と解するのが相当といえます。
そして、逮捕の必要性については、刑事訴訟規則143条の3が「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と定めていますので、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの有無・程度が逮捕の必要性の有無の判断において重要であると推測されます。
※ 勾留の要件である勾留の必要性の有無の判断と同様に、身柄拘束の必要性(証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等)と身柄拘束によって被疑者が被る不利益を比較衡量して、前者が後者を上回る場合には逮捕の必要性があると判断するのが学界の多数説ではないかと思います。
以上を前提として、立花氏の通常逮捕について、逮捕の必要性があったかどうかを検討しますと、名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑」(刑法230条)であり、殺人や強盗、放火等の犯罪に比べると、その法定刑は重くありません。
このように、法定刑が比較的軽いもの(殺人等の犯罪のように、有罪となった場合に原則として実刑判決が下るものではなく、略式起訴で罰金刑にとどまったり、拘禁刑に執行猶予が付される可能性が高い犯罪)については、実刑判決をおそれて逃亡する可能性が高いとはいえませんし、わざわざ証拠隠滅を図る可能性も高いとはいえません(あくまで一般論です)。そうすると、立花氏については、逮捕の必要性が否定されるように思えます。
しかし、立花氏には、執行猶予中であるという特殊な事情があります。執行猶予中に罪を犯し、公判請求され裁判で有罪と認定された場合、原則として実刑判決が下りますし、執行猶予が取り消されて、過去の分もあわせて刑務所に服役することになってしまいます(なお、罰金刑に処された場合には執行猶予は取り消されません。)。この不利益は相当大きなものですので、一般的に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると認められやすくなります。
実際に、立花氏が逃亡するかどうかではなく(人柄、性格に照らせば逃亡するような人ではないといった主張はあまり意味をなさず)、立花氏が置かれた状況を客観的にみて、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性を根拠づける事情があると合理的に推認できるかどうかが、逮捕の必要性の有無の判断にあたって重要ということです。
ただし、逮捕に続いて、勾留が認められるかどうかという点については、別途検討が必要になります。勾留が認められると原則として10日間、延長されれば20日間の身柄拘束が認められてしまいます。このように、逮捕に比べて、身柄拘束期間が長期にわたりますので、勾留の要件である、住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれと勾留の必要性は、いずれも厳格に判断すべきとされています(実際には、抽象的なおそれがあるにとどまるのに勾留決定がなされている事案は少なくないように感じますが、それでもなお、逮捕における必要性の有無の判断に比べると厳格に判断されていると思います。)。そのため、立花氏の場合、勾留請求が認められない(裁判官が認めない)可能性は十分あると思いますし、いったん勾留決定がなされても、弁護側が準抗告を申し立てることにより、当該勾留決定の判断が覆る可能性もあるでしょう。
したがって、立花氏の事案においては、勾留決定が出た場合には、ほぼ間違いなく、弁護側が準抗告を申し立てるのではないかと思います。個人的には、逮捕や勾留を安易に認めるべきではないと考えていますので(身柄拘束による不利益は、大多数の人にとって大変大きいものだからです。)、海外逃亡を防ぐべくパスポートを弁護人が預かるといった事情があるならば、勾留は認めるべきではないと考えます。立花氏は日本全国で有名であり、国内逃亡を図ることは極めて困難でしょうから、海外逃亡を防止する措置さえ講じられるのであれば、身柄拘束は不要と思います。過去に、カルロスゴーンがプライベートジェット機で海外逃亡しましたが、これは例外中の例外とみるべきでしょう。
タグ
2025年11月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
医師、歯科医師の応召義務
7月も後半になりました。今月、45歳の誕生日を迎えて肉体的な衰えを日々感じているので、これまで以上に健康には気をつけて過ごしていきたいと思います。
さて、弊所の顧問先には、クリニックや歯科医院が複数あり、時折、応召義務について質問を受けることがありますので、ここで簡単に説明したいと思います。
応召義務については、医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項がそれぞれ下記のように定めています。
医師法第19条1項
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
歯科医師法第19条1項
「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
※ なお、薬剤師法第21条には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合に は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあり、また、保健師助産師看護師法第39条1項にも「業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあります。これらも上記の応召義務と類似した規定ですが、このブログでは説明を省きます。
医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項を素直に解釈すれば、原則として、患者から診療の求めがあった場合には、診療しなければならないが、正当な事由がある場合には例外的に診療を拒否できるということになります。
それでは、上記にいう「正当な事由」にはどのような事情が当てはまるのでしょうか。
この点については、厚生労働省が令和元年12月25日に公表した「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発1225第4号)が大変参考になります。
上記においては、応召義務に反するか否かの判断においては、「患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」が最も重要な考慮要素であると明記されています。
また、診療を求められたのが診療時間・勤務時間内かどうか、患者と医師・歯科医師の信頼関係も次に重要な考慮要素であるとされています。
詳細に記載することは控えますが、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間内である場合には、医師や歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下における医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性等を総合的に勘案して、事実上診療が不可能といえる場合でない限り、診療しなければならないということになります。一方、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間外である場合には、応急的に必要な処置をとることが望ましいものの、診療を拒否しても原則として公法上・司法上の責任に問われることはない(応召義務違反にならない)とされています。
では、緊急対応が必要でない事案の場合はどうなるのでしょうか。
この場合であっても、診療を求められたのが診療時間内である場合には、原則として患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要があるとされていますが、正当な事由の有無は、上述した医師や歯科医師の専門性・診察能力、医療提供の可能性、設備状況等のみならず、患者と医師・歯科医師の信頼関係も考慮して判断されることとなり、かつ、緊急対応が必要な事案である場合と比較して、その判断(解釈)は緩やかになされるとされています。
当然、診療を求められたのが診療時間外である場合には、診療を拒否しても応召義務違反にはならないということになります。緊急性がない以上、このような判断は妥当でしょう。
その上で、緊急対応が必要でなく、かつ、診療時間内の場合であっても、患者の迷惑行為が認められるケース(暴言、暴行、理不尽かつ執拗なクレーム等)、「悪意」による医療費の不払いが認められるケース(なお、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合は悪意のある未払いであると推定される場合もあります。)、医学的に入院の継続が必要ないケース、病状に照らして他院への通院(転院)が相当なケース、言語が通じない、宗教上の理由等によって結果として診療行為そのものが著しく困難になるケース(ただし、単に患者の年齢や性別、人種、国籍、宗教等のみを理由とする場合を除く)等は、診療を拒否できる正当な事由があると判断される可能性があるとされています。
以上、厚生労働省の見解に沿って説明してきましたが、緊急対応が必要でない事案において、応召義務が問題となるのは、主として患者と医師・歯科医師の信頼関係に関するものが多いと感じています。
基本的には、医師・歯科医師は、患者に対して説明義務を負っていますので、同説明義務に基づき、できるだけ丁寧に説明することを心がけて患者との信頼関係を構築すれば、トラブルになることは少ないと思いますが(説明が足りないと、患者が不安に思い、不満も募るのはやむを得ないでしょう。)、中には、何度説明しても納得せず、暴言を繰り返す、何度も同じ説明を求めて長時間にわたって医師・歯科医師を事実上拘束する、医師・歯科医師の指示に従わずに理不尽な要求を繰り返すといった人も残念ながら一定数存在します。このような場合には、他の患者に与える影響等に照らして、診察を拒否することもやむを得ないと考えますが、その場合であっても、例えば、「これ以上、暴言を吐くなら、信頼関係を維持できないので、診療できなくなる」等と伝えて、事前に予告(注意)しておくのが無難と思います。突然、診療を拒否すると、トラブルに発展しやすいので、この事前の予告(注意)は重要です。
タグ
2025年7月22日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
古物営業法
東京は、いつの間にか、真夏日続きになりました。日中にバイクに乗って渋滞にはまると、なかなか辛いものがあります。最近は、ありがたいことに新規の相談をたくさんいただけていて、忙しい日々を過ごしています。これまでに取扱い経験の少ない案件又は法律構成に悩む案件については、調査に時間を要するので、なかなか大変ですが、法律書や裁判例を読み解く作業は楽しく、「忙しいのに楽しい」という感覚で仕事をしています。
さて、最近、古物営業法に関する相談を受けて少し調べましたので、この法律について簡単に説明しようと思います。
古物営業法の目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」にあると定められています。要するに、中古品の売買には、盗品が含まれていたりしますので、許可なく中古品の売買を業とすることは認めないというものです。ここにいう「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されており、基本的にあらゆる中古品が含まれることになります。ちなみに、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは新古品を意味し、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは修理やレストアを施したものを意味します。
ただし、古物営業の典型例は「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」、「古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業」であり、「営業」であることがポイントです。個人がいらなくなった中古品をメルカリやヤフオクに単発的に出品して売ることは、基本的に「営業」には該当しないので、都道府県公安委員会の許可を受ける必要はないということになります。利益を得る目的(営利目的)で売買等の同種の行為を継続することが「営業」です。
ですので、中古車や中古バイク、中古ピアノ等の売買をしている業者さんは、すべからく、古物営業法が定める許可(都道府県公安委員会による許可)を得ている(得なければならない)ということになります。また、個人がヤフオクやメルカリで中古品を販売する場合であっても、利益を得る目的で継続的に行うと、それは「営業」にほかなりませんので、やはり許可が必要ということになります。
許可を得ているかどうかについて、どうやってわかるの?と疑問を抱く方がおられると思いますが、古物商は、営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならないと定められていますので、営業所に行って標識を見れば一目瞭然ということになります。逆に、営業所に標識が掲げられていなければ、怪しいということになりますね。掲示するのを忘れているだけの人もいるかもしれませんが。
上記の古物商の許可を得るには、公安委員会に対し、所定の事項を記載した許可申請書を提出する必要があります。ただし、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者や過去に拘禁刑以上の刑に処せられたか、古物営業法第31条や刑法235条(窃盗)、刑法247条(背任)、刑法254条(遺失物等横領)等の罪によって罰金刑に処され、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者等、一定の条件に該当すると、古物商の許可を得ることができません。これらの犯罪を犯した人は、相当期間が経過していないと、信用性に欠けるということでしょう。ちなみに、執行を受けることがなくなった日とは、やや分かりにくいですが、執行猶予判決を言い渡された後にその執行猶予期間が満了した日が典型例です。
古物商の許可を得ずに、古物営業をしてしまうと、古物営業法第31条により、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになるので、要注意です。
古物営業法には、ほかにも種々の規制が定められていますが(帳簿等への記載や警察による販売差し止め(古物の保管)など)、これ以上書くと、さらに長くなってしまうので、今回は簡単な説明にとどめようと思います。
もっと詳しく知りたいという方は、警察庁生活安全局長が令和6年8月14日に発した「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」を参考にするとよいと思います。
いつになるかわかりませんが、大好きな中古バイクを販売する仕事を始めようと思ったときは、ちゃんと古物商許可を得て行いたいと思います。まぁ、弁護士業を引退してからでしょうから、その日が本当にやってくるのかは微妙ですけども。
タグ
2025年6月21日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
駐車場内の交通事故
気づいたら3月ももうすぐ終わりそうです。もうすぐ4月で、桜の季節ですね。ここ数年、桜を見に行っていないので、今年はバイクで桜の名所に行ってみたいと思う一方で、相変わらず仕事に追われていて、そんな暇ないなという現実がありまして、あぁ、どうしたものかと悩みます。
年明けから、ゴルフにはよく行っているのですが、そうすると、ほかに休みをとっている余裕がないというのは至極当然とも思えるところでして。お花見はゴルフの帰りに行くしかないかなと思いますね。
さて、今日は、相談の多い、駐車場内の事故(交通事故)について、簡単に解説しようと思います。
駐車場内の事故については、通路進行車、駐車区画進入車、駐車区画退出車という3つのいずれかに自動車を区分した上で、過失割合を算定していきます。このときに参考になるのは、もちろん、別冊判例タイムズ38(民事交通訴訟における過失相殺率の」認定基準)ですが、基本となる過失割合のケースが合計5つしかないので、これだけでは実際に生じた駐車場内事故について、個別具体的に過失割合を算定するのが難しいといわざるを得ません。
そのせいもあってか、交通事故相談において、駐車場内事故についての相談を受けることがよくあります。
まず、原則として、1⃣通路進行車同士の事故の場合、過失割合は50対50、2⃣通路進行車と駐車区画退出車の事故の場合、過失割合は30対70、3⃣通路進行車と駐車区画進入車の事故の場合、過失割合は80対20、4⃣歩行者と自動車の事故の場合、過失割合は10対90になります。
駐車場は、あくまで駐車のための施設であり、通路から駐車区画に進入することは駐車場の設置目的にかなう行為であるという理由により、駐車区画進入車が最も優先され、通路進行車、駐車区画退出車よりも、過失割合が低くなります。
それならば、駐車区画退出車の方が通路進行車よりも優先される(過失割合が低くなる)のでは?という疑問を抱く方もいると思いますが、駐車区画退出車は、通路に進入する前の段階で駐車区画内に停車していることから、通路進行車よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができるはず、という理由により、駐車区画退出車の方が通路進行車よりも重い注意義務が課され、その過失割合は高くなるというわけです。
それでは、駐車区画進入車同士の事故や駐車区画退出車同士の事故の場合、駐車区画進入車と駐車区画退出車の事故の場合の過失割合はどうなるのでしょうか。
これらについて、5⃣駐車区画進入車同士の事故と6⃣駐車区画退出車同士の事故の場合、課されている注意義務はそれぞれ同じですので、過失割合は50対50となるのが原則と思われます。
次に、7⃣駐車区画進入車と駐車区画退出車の事故の場合、上記のとおり、駐車場内では駐車区画進入車が最も優先されますので、駐車区画進入車よりも駐車区画退出車の方が過失割合は高くなります。では、その過失割合はどうなるか?と問われると難しいところですが、原則として20~30対80~70になるのではと思います(あくまで私見です。)。
しかし、上記はあくまで基本的なケースを想定したものであることに注意しなければなりません。いずれの車両が先行していたのか、通路の広さはどうか、徐行していたかどうか、見通しはどうか等の個別具体的な事情によって過失割合は変わることを意識しておく必要があります。
なお、相談において、「こちらは停止していたのに、相手が衝突してきた。だから過失はない。」といった相談を受けることがよくありますが、衝突する直前(1~2秒前)に停止しても、それは直前停止といって、過失割合を減ずる要素としてはほぼ考慮されません。また、直前停止にはあたらないとしても、停止位置が悪いということにより、過失があると判断されることもあります。例えば、駐車区画の枠にはみ出る形で停車していたような場合ですね。
ということで、簡単に解説してみましたが、最終的には、裁判例等を踏まえて個別具体的に過失割合を判断(推認)していくことになることが多いので、過失割合について納得がいかないという場合には、弁護士に(できれば複数の弁護士に)相談して見解をうかがってみることをお勧めします。
タグ
2025年3月29日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
訃報
最近、どうやら夜型人間に戻りつつあり、午後に出勤して翌日午前(深夜)まで働くという勤務を繰り返しています。
朝の方が頭が冴えている、深夜の何倍もはかどる、という話をよく耳にするので、このような深夜型の勤務はよくないのかもしれません。ただ、実際には、深夜ゆえに静寂の中で集中できるというメリットもあるのではないかと思います。さすがに、深夜に事務所の電話が鳴ることはなく(ごくたまに電話があって、応答して法律相談に対応することもありますが)、電話で集中力が途切れることがないのはありがたいところです。
とはいえ、午前5時から午前8時の早朝勤務も同様に静かなので、集中したいなら、早朝に来て夕方に帰るべし、というツッコミを受けてしまいそうです(笑)。
さて、ここから本題ですが、最近、京都大学法学部の潮見佳男教授が急性心不全により逝去されたというニュースを見ました。潮見先生といえば、民法の大家でして、私が司法試験受験生だった頃は、潮見先生の基本書と内田先生の基本書が受験生に大人気だったことを思い出しました。どちらかといえば、要件事実を意識した書きぶりの潮見先生の基本書の方が人気が勝りつつあったくらいだと記憶しており、私は新世社の「基本講義 債権各論Ⅰ」と「基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為方」を愛用していました(どちらも基礎から優しく解説してくれています)。そして、司法試験に合格してからも潮見先生の著作を参考にすることはよくあり、とてもありがたかったです。
信山社の「プラクティス債権総論」はとてもわかりやすくて、受験生から実務家まで幅広く利用できるものですし、債権法の分野でいろいろ調べてもよくわからないときは、同じく信山社から出ている法律学の森シリーズ(「新債権総論1」、「新債権総論2」、「新契約各論1」、「新契約各論2」など)を読んでみたりしています。余談ですが、私が受験生だったときに、「法律学の森シリーズは難しすぎて、森に迷い込むから読まないほうがいい」と某先生から言われたことがあります(笑)。
最近、「詳解 相続法」の第2版が発売されたばかりなので、お亡くなりになったというニュースを見ても実感が湧かないのが正直なところです。そもそも、潮見先生と面識はなく、あくまで文献を通して私が一方的に存在を知っているだけなので、実感が湧かなくて当然かもしれません。
いずれにせよ、とても残念です。潮見先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。
タグ
2022年8月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
労働法関連書籍の改訂が目白押しです
再び、コロナ感染者数が急激に増大しつつありますね。一体いつになれば落ち着くのかと思いますが、ここが踏ん張りどころなんでしょう。
さて、これまでにこのブログで、令和3年版労働基準法の上巻と下巻、リーガル・プログレッシブシリーズの労働関係訴訟ⅠとⅡが改訂され、いずれも労働問題を取り扱う弁護士にとって有用とお伝えしました。
そんな中、日本労働問題弁護団編著の「新・労働相談実践マニュアル」が発売されました。この書籍はかなり前に発売されて改訂を繰り返しているものでして、とても信頼性のある書籍です。そういえば、私が弁護士になって間がないときに、改訂前のものを購入し、労働事件を解決するにあたって何度も目を通した思い出があります。この本と日本労働問題弁護団編著の「労働審判実践マニュアル」、菅野和夫先生の「労働法」(弘文堂)でなんとかやれていたといっても過言ではありません。
日本労働問題弁護団編著の上記書籍は、東京では裁判所の地下の書店や弁護士会館の地下の書店で売られていますが、それ以外の都道府県ではなかなか見つからないかもしれません。欲しい人は、日本労働問題弁護団のホームページから購入を申し込むとよいと思います。この本も、労働問題を取り扱う弁護士にとって有用です。
それにしても、労働法関係の重要書籍の改訂が相次いでいますね。事務所で購入する場合はさておき、弁護士個人で購入するとなるとけっこうな値段となるので、ちょっと大変かもしれません。同じ事務所の弁護士で買い分けするなどしてもいいかもしれませんね。
タグ
2022年1月21日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
労働事件をやるなら買いだと思う。
今年は、昨年に続いて労働事件を扱う実務家にとって重要な本の改訂が目白押しな感があります。
というのも、以前にブログで紹介したリーガル・プログレッシブシリーズの「労働関係訴訟」が久々に改訂されたのに引き続き、同様に実務家が労働事件を取り扱うにあたって指標となる労務行政発行の「労働法コンメンタール」も改訂・発売されたからです。
上記の本の正式名称は「令和3年版 労働基準法 上巻」と「令和3年版 労働基準法 下巻」であり、厚生労働省労働基準局が編集している点で信頼性がとても高いと思います。労働基準法のコンメンタールはほかにも発売されていますが、国(行政)がどういう見解に立っているのかを確認する意味でも有用な書物です。お値段はどちらも税込み約7500円となかなかお高いのですが、滅多に改訂されないので、買っておいて損はないと思います。なお、改訂前のものは「平成22年版 労働基準法」の上下巻でした。実に11年ぶりの改訂なわけです。
労働事件に興味のある修習生や労働事件を取り扱う事務所に入所予定・入所した修習生・新人弁護士の皆さんには強くお勧めしたいと思います。
タグ
2022年1月11日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
ようやく発売された改訂版
前回の更新に続けて、早いペースでの更新です。
さて、今回、私が以前にこのブログで何度かおすすめしたことがあるリーガル・プログレッシブシリーズの1冊である「労働関係訴訟」(青林書院)の改訂版が発売されたので、ちょっと嬉しくなって更新しようと思った次第です。
改訂前のものは、2010年3月に発売されていたので、実に10年半年ぶりの改訂となります。著者の渡辺弘さんは東京地裁労働部の元部長(元裁判官)ですので、上記書籍の信頼性は高いと思います。実際、旧版を読んでいてとても勉強になりましたし、役にも立ちました。
そんな上記書籍が、この度の改訂で、ボリュームをアップして、2分冊となって登場しましたので、労働事件に携わる弁護士(特に新人の弁護士)には以前と同様に強くおすすめしたいと思います。
なお、2,3年おきに改訂されるとなると買い替えに若干躊躇してしまうのですが(ほぼほぼ内容に大差がない改訂もありますので)、今回のように10年ぶりでの大改訂となると気持ちよく買い替えることができますね(笑)。
タグ
2021年12月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
侮辱罪で在宅起訴?
ここ最近仕事がなかなか終わらないのですが、今日は久々に深夜まで事務所に残って仕事をしています。
そんな中、ふとインターネットを見ていたら、飛行機内でマスクの着用方法を注意された67歳の男性が注意した女性に向かって「コロナみたいな顔してからに」と言い放ったという事案で、男性が在宅起訴されたというニュースを目にしました。
ニュースによれば、男性は否認しているとのことですので、罪を認めていることを前提になされる略式起訴という手続をとることはできません。したがって、検察としては、不起訴処分とするか起訴するかの二者択一しか選択肢がないことになり、上記の事案では、十分な証拠があって犯罪を立証できる,男性の犯情は悪い(注意を受けたことに逆上して、他人に対して「コロナみたいな顔」って言うのは、無礼すぎますからね。)ということで起訴されたものと考えます。
上記について、侮辱罪で起訴されるのは珍しいなぁと気になって調べてみたら,今年の9月に侮辱罪の法定刑を現行の「拘留・科料」から「1年以下の懲役若しくは禁固又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる刑法改正案が法務大臣に提出されていたことを知りました。上記の在宅起訴の背景にはこの厳罰化の流れも関係しているのかもしれません。
確かに、拘留(30日未満の身柄拘束)と科料(1000円以上1万円未満の財産刑)という刑罰は上限が軽すぎるように思いますので、改正には反対しませんが、個人的には、厳罰化よりも、侮辱行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料の金額を増額した方が侮辱行為を効果的に抑制できるのではないかと思っています。実際には,侮辱されたといって告訴しても,よほどの証拠(録音,録画、目撃者,SNS上のメッセージ等)がない限り,警察は簡単に捜査してくれないと思うからです。
現状,侮辱された場合の慰謝料額は低廉にとどまっておりますので,弁護士に依頼して民事訴訟を提起し、慰謝料の回収を図ろうとしても,弁護士費用の方が慰謝料よりも高くつくことが多いという事情があります。そのため,侮辱を受け,その確たる証拠を有していても,泣き寝入りせざるを得ないという人は相当数おられると思います。慰謝料を高額化すれば,このような泣き寝入りの事態を減らすこと,侮辱行為の抑制につながると思いますが,他方で,表現行為の委縮にもつながりかねないところなので、単純に慰謝料の高額化を図るわけにはいかないのが悩ましいところです。
実際には,侮辱行為に該当するか否かの判断が難しい表現はたくさんありますからね。
こんな風にいろいろ考えてこのブログを書いていたら、時間が思いのほか経過していたので、今日はこのへんにしときます。
タグ
2021年12月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学