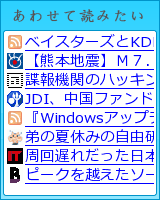2026年業務開始
皆様、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
琥珀法律事務所は、本日(1月5日)から業務を開始しました。昨年は、12月26日をもって業務を終了していますので、従業員一同にとっては久々の長期休暇になったのではないかと思います。私自身は、年末まで相談等に対応しておりましたが、12月31日から1月4日まではゆっくり休むことができました。この期間に、弁護士の中村真先生著作の「弁護士という仕事」(有斐閣)という本を読破したのですが、弁護士という業務特有の悩み等がイラストとともに記載されていて、楽しく読めましたね。業務の合間に息抜きとして読むのにちょうどいい書籍だと思います。
年末年始は京都で過ごし、1月1日に初詣で下鴨神社に行きましたが、参拝客の行列が長蛇の列となっていたので、その日のお参りは諦めて1月2日に再び下鴨神社に行きました。しかし、1月2日も1月1日同様に長蛇の列になっており、その日に東京に戻る予定だったので、やはりお参りは諦めることにしました。結局、この2日間は参道に出ていた屋台で食べて帰るだけという結果になってしまったので、1月中に大阪出張に行った際に、今度こそ下鴨神社にお参りしたいと思います。
さて、今日から気を改めて、再び仕事に邁進していきますが、弁護士を取り巻く環境は年々厳しくなっていますので(特に東京、大阪等の大都市圏)、業務範囲の拡大や新たな支店展開は控えて、足元を固めていく1年にするつもりです。1つ1つの案件を対して大切に対応し、依頼者の信頼を得られるように頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
2026年1月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
F355が旅立ちました…
今年も残すところわずかですね。
琥珀法律事務所は、12月26日が年内最終営業日でして、年明けは1月5日から営業開始となります。
今年は、六星占術によれば、大殺界ということもあって、いろいろと大変でした。その中でも今年1年で最も大きな出来事といえば、縁あってお誘いいただいた曲川サーキットで愛車のF355(GTS マニュアル車)をクラッシュさせてしまい、廃車になったことかなと思います。
事故自体は11月のことでしたが、現実を受け入れるのに時間を要してしまいました。
残ローンも相当額残っていた上で、サーキットからガードレール等の修理代も請求される状況にあり、一体どうしたものかと途方に暮れていたのですが、全損扱いとなったF355がそれなりの金額で売れたことにより(購入先の車屋さんがレッカーしてくれて、業者への売却を頑張ってくれました。)、無事に残ローンと修理代をギリギリ支払えてスッキリしたので、今回、こうやってブログに書けるくらいに回復しましたww
今回の事故で気づいた注意すべきポイントは、
1 タイヤが暖まるまでは慣らし運転でゆっくり走行しないと事故する
2 年式の古いタイヤは硬化しているので、特に要注意
(私のF355が履いていたタイヤは2019年式でした)
3 自身の運転技術を過信しない
4 サーキット走行中の事故、ダート走行中の事故は一般の車両保険の対象外
ということですかね(1と2は常識レベルの知識らしいんですけど…)。
特に、上記4は本当に気をつけるべきでして、修理費用どころか、レッカー費用すら保険の対象外となってしまいます。
また、曲川サーキットって、けっこうカーブがきついところがあるので、初心者は慎重に走行した方がいいと思い知らされました、後の祭りですが…。
古めのフェラーリはオートマ(F1)かマニュアルかで価格帯が全く異なり、後者の方が前者よりも高額な価格帯を形成しています。私のF355は、マニュアル車で走行距離も少なかったので(2万キロ未満でした。)、事故に遭わずに売却していたら、それなりの高額になっていたと思います。それが事故によって吹っ飛んだので、事故直後はなかなか現実を受け入れることができませんでしたね。大殺界恐るべし…なんて思っていましたが、私の過失による単独事故なので、自業自得というほかありません。
とはいえ、何かいいことないかなと思って、数年ぶりに年末ジャンボ宝くじを購入しました。これが高額当選していたら、懲りずに再度、フェラーリを購入したいと思います、今度は長期ローンではなく、一括でww
2025年12月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
令和7年度マンション管理士試験
今年も残すところ20日程度となりました。今年の年末は、金融機関を除いて大型連休が取得可能な感じですね。琥珀法律事務所は、12月26日を最終営業日とし、来年は1月5日月曜日から業務を開始します。
さて、今年もマンション管理士試験を受験してまいりました。最初に買った参考書の発行年が2019年だったので、早6回も受験したということになります。で、今回の結果は…というと、自己採点で32点でして、順調に撃沈しました。おそらく合格予想点は37点以上になると思われ、5点以上足りないということになります。
受験直後の感触では、昨年よりもやや優しくなったように思ったのですが、そもそも、絶対的な準備が足りておらず、知らない問題(単純な暗記問題)を出されるとお手上げでした。
昨年の受験直後の時点では、来年こそ受かるぞと意気込んでいて、最低1か月は準備しよう(勉強しよう)と思っていたのですが、今年の秋ごろにはそんなことを忘れてゴルフの予定を入れすぎてしまい、これに相まって急な仕事の対応もあって、案の定、勉強時間が全く足りませんでした…。
己の自制心のなさ、覚悟のなさを恥ずかしく思いますね…。6回という受験回数は司法試験よりも多いですww いわゆるベテラン受験生の仲間入りという感じですね。
9月~11月はゴルフのオンシーズンですので、ゴルフ好きの私としては、11月末の日曜日という試験日設定は厳しいものがあります。2月とかに日程変更されないかなぁなんて空想にふけってしまいますが、現実は、来年も11月末に実施されるでしょう。いずれにせよ、さすがにもう受かりたいです。
マンション管理士は名称独占資格に過ぎず、独占業務があるわけではありませんので、取得してもしなくてもよい資格(特定の仕事を行うにあたって必須の資格とはいえない)といえ、それゆえに危機感がないのかもしれません。
ただ、いつまでもこの資格の勉強にかかりきりになっている場合ではなく、他の資格に関する勉強も行っていきたいと思っていますので、2026年度のマンション管理士試験に合格することをもって、この分野の勉強をいったんストップしたいと思います。三度目の正直は過ぎてしまっているので、7度目の正直を実現すべく頑張ります。
2025年12月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
令和7年度貸金業務取扱主任者試験
昨日、今年初の資格試験である貸金業務取扱主任者試験を受験してきました。貸金業者は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数が1:50以上の割合となるように貸金業務取扱主任者を置かなければなりませんので、貸金業を行う者にとっては重要な資格です。
そのため、今後、貸金業を行う予定のない(現時点で貸金業社に入社する予定のない)私にとっては不要な資格ということになりますが、琥珀法律事務所では交通事故事件・労働事件と並んで債務整理事件も多数取り扱っているので、貸金業法や利息制限法をこの機会により深く勉強しようと思って、受験を決意したのです。実際、勉強を通じて、貸金業法、利息制限法(特に貸金業法)の条文に詳しくなりましたし、貸金業者向けのガイドラインも学んで、犯罪収益移転防止法や個人情報保護法等の他の法律も復習することができました。
貸金業務取扱主任者試験の合格率は毎年30パーセント前後ですので、宅建試験(合格率15~18パーセント程度)に比べると易しいといえます。実際、過去問5年分に目を通しましたが(全部解くことは時間的に無理でしたが、それなりに解答・解説を読み込みました。)、宅建やマンション管理士試験(合格率7~8パーセント程度)に比べて、素直な問題が多く、内容も平易で取り組みやすいと感じました。
で、昨日の試験の出来についてですが、意外にも、想像していた以上に難しく感じ、けっこう苦戦しました。当日の試験開始直前まで過去問題集に目を通し、合格はできるかなと一定の自信をもっていたのですが、いざ試験が始まると初見の選択肢がいくつもあって焦りましたね。絶対時間が余ると思っていたのに、実際には2時間フルに使って50問を解き終えました。これが試験の怖いところですね。
で、各種予備校が出す解答速報を心待ちにしていたのですが、貸金業務取扱主任者試験については、受験者数が宅建等に比べて少ないためか、試験当日に解答速報は出されず、TACが11月18日17時に発表する解答速報が最短のようでした。
ということで、気になる私は、試験後に事務所で1件相談業務に対応した後に帰宅し、そこから解答を調べました。以下、私なりに調べた解答ですが、全て合っているかどうかは自信がありません(責任をおいかねます)。このブログを見た貸金業務取扱主任者試験受験者の方は、明日のTACの発表と照らし合わせてもらえればと思います。
14224 14322 41332(12問目は1ではなく2かも?)
23123 42314 41332
41142 33434 24323 41122
ちなみに、自己採点では私の点数は30点台後半でした。それなりに勉強したのに財務及び会計に関することの問題(48~50問)を全部間違えてしまった上に、民法の問題も2問間違てしまって(根抵当権の問題と期限・期間の問題)、もっと勉強しないといけないと改めて思いました。受験前は40点以上とると意気込んでいたので、やや残念に思いますが、試験自体はマークミスがない限り(又は上記解答例が間違っていない限り)、合格できていると思いますので、結果オーライかなと考えて、次の試験に向けて勉強を開始します。
2025年11月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
通常逮捕の要件
今月も3分の1を経過しました。今年もあと2か月弱ですが、インフルエンザが世間で流行っていますので、体調管理に気をつけて過ごしていきたいと思います。
さて、昨日、N国党の立花孝志氏が名誉毀損の被疑事実により通常逮捕されたとの報道がありました。この逮捕について、逮捕の必要性があったのかという点が問題として取り上げられており、X等で投稿が繰り返されています。そのため、参考までに、このブログでも簡単に説明しようと思います。
通常逮捕については、刑事訴訟法199条1項本文が「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と定めています。この規定の仕方に照らせば、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」さえあれば、逮捕状の発付を受けて通常逮捕が可能なように読めますね。
しかし、199条1項但し書きは、上記本文について、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく、出頭の求めに応じない場合に限ると定めています。また、199条2項は、裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官等の請求に応じて逮捕状を発すると定める一方で、同条2項但し書きにおいて、「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とも定めています。
上記の条文構造に照らせば、逮捕状の発付にあたっては、逮捕の必要性があることを要件と解することができ、199条1項但し書きが30万円以下の罰金等に当たる軽微な犯罪について、住居不定や任意の呼び出し不出頭を要件としているのは、軽微な犯罪の場合には類型的に逮捕の必要性が認められにくい(小さい)と捉えているためと考えられます。
※ 罰金に処されることをおそれて逃亡を図ったり、証拠隠滅を画策する人は少ないでしょう。
また、刑事訴訟規則142条は、逮捕状の請求書に帰しすべき事項を定めていますが、その記載事項の中には「被疑者の逮捕を必要とする事由」が含まれていますし、同規則143条1項は「逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。」と定めていますので、やはり、逮捕の必要性は逮捕状発付の要件と解するのが相当といえます。
そして、逮捕の必要性については、刑事訴訟規則143条の3が「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と定めていますので、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの有無・程度が逮捕の必要性の有無の判断において重要であると推測されます。
※ 勾留の要件である勾留の必要性の有無の判断と同様に、身柄拘束の必要性(証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等)と身柄拘束によって被疑者が被る不利益を比較衡量して、前者が後者を上回る場合には逮捕の必要性があると判断するのが学界の多数説ではないかと思います。
以上を前提として、立花氏の通常逮捕について、逮捕の必要性があったかどうかを検討しますと、名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑」(刑法230条)であり、殺人や強盗、放火等の犯罪に比べると、その法定刑は重くありません。
このように、法定刑が比較的軽いもの(殺人等の犯罪のように、有罪となった場合に原則として実刑判決が下るものではなく、略式起訴で罰金刑にとどまったり、拘禁刑に執行猶予が付される可能性が高い犯罪)については、実刑判決をおそれて逃亡する可能性が高いとはいえませんし、わざわざ証拠隠滅を図る可能性も高いとはいえません(あくまで一般論です)。そうすると、立花氏については、逮捕の必要性が否定されるように思えます。
しかし、立花氏には、執行猶予中であるという特殊な事情があります。執行猶予中に罪を犯し、公判請求され裁判で有罪と認定された場合、原則として実刑判決が下りますし、執行猶予が取り消されて、過去の分もあわせて刑務所に服役することになってしまいます(なお、罰金刑に処された場合には執行猶予は取り消されません。)。この不利益は相当大きなものですので、一般的に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると認められやすくなります。
実際に、立花氏が逃亡するかどうかではなく(人柄、性格に照らせば逃亡するような人ではないといった主張はあまり意味をなさず)、立花氏が置かれた状況を客観的にみて、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性を根拠づける事情があると合理的に推認できるかどうかが、逮捕の必要性の有無の判断にあたって重要ということです。
ただし、逮捕に続いて、勾留が認められるかどうかという点については、別途検討が必要になります。勾留が認められると原則として10日間、延長されれば20日間の身柄拘束が認められてしまいます。このように、逮捕に比べて、身柄拘束期間が長期にわたりますので、勾留の要件である、住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれと勾留の必要性は、いずれも厳格に判断すべきとされています(実際には、抽象的なおそれがあるにとどまるのに勾留決定がなされている事案は少なくないように感じますが、それでもなお、逮捕における必要性の有無の判断に比べると厳格に判断されていると思います。)。そのため、立花氏の場合、勾留請求が認められない(裁判官が認めない)可能性は十分あると思いますし、いったん勾留決定がなされても、弁護側が準抗告を申し立てることにより、当該勾留決定の判断が覆る可能性もあるでしょう。
したがって、立花氏の事案においては、勾留決定が出た場合には、ほぼ間違いなく、弁護側が準抗告を申し立てるのではないかと思います。個人的には、逮捕や勾留を安易に認めるべきではないと考えていますので(身柄拘束による不利益は、大多数の人にとって大変大きいものだからです。)、海外逃亡を防ぐべくパスポートを弁護人が預かるといった事情があるならば、勾留は認めるべきではないと考えます。立花氏は日本全国で有名であり、国内逃亡を図ることは極めて困難でしょうから、海外逃亡を防止する措置さえ講じられるのであれば、身柄拘束は不要と思います。過去に、カルロスゴーンがプライベートジェット機で海外逃亡しましたが、これは例外中の例外とみるべきでしょう。
2025年11月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
ゴルフ三昧
あっという間に10月後半に差し掛かり、今年もあと2か月強で終わりですね。
つい先日まで蒸し暑い日が続いていたのに、いつの間にか肌寒くなっていて、急いで
長袖の服を引っ張りだしました。
さて、10月といえばゴルフのベストシーズンです。ありがたいことにたくさんの方に
お招きいただいて一緒にプレーをしたおかげで、最近、2年ぶり?にベストスコアを更新できて、ベストスコアが95になりました(それまでは100でした)。
やっと念願の100切りをはたせたので、気持ちが舞い上がり、これからは100前後で
プレーできるかな?なんて思っていたのですが、直近の2回はいずれも124、125と絶不調でした…。これがゴルフの醍醐味ですよねww
次は、90切りを目指して頑張るつもりですが、100切りまでに何年もかかったので、
90切りをするのにも数年かかるのではないかと…。
来月も適度にゴルフをするつもりですが、寒いのが苦手なので、12月~2月はゴルフに行く回数が減りそうです。とはいえ、打ちっぱなしでの練習は定期的に続けて、しっかりと
アプローチができるようにしたいと思っています。
2025年10月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
大雨による被害
先週はほぼ熊本事務所、福岡事務所で過ごしており、先週土曜の夜に東京に戻ってきました。今日は、昼に面談予定があったので、立川事務所で一日執務しています。
9月も半ばに差し掛かって、ようやく日中の暑さも和らいできたと感じています。
さて、私が九州に出張していた間に、三重県や静岡県、東京あたりで大雨が降って、
地下駐車場がいくつか冠水したというニュースを目にしました。大切な車が水に浸かってしまって、使用不可になるのは精神的にも経済的にも負担が大きいことは当然であり、被害に遭われた方の心中は察するに余りあると思います。
上記のケースでは、車のエンジン部分を超える水位まで水没していた様子が垣間見られました。このように、エンジン部分を超えるところまで水につかってしまうと、全損扱いになることが多いようです(ハイブリッド車や電気自動車は特にそういえます)。
そうすると、買い替えを前提に検討せざるを得なくなるので、被る損害は甚大というほかありませんが、このような自然災害による水没のケースでも、自動車保険(任意保険)に車両保険がついていれば補償の対象となります(ただし、地震・噴火を原因とする津波による浸水を除きます。)。
したがって、まずは、自身が加入する任意保険に車両保険がついているかどうかを確認されるのがよいと思います。車両保険といえば、盗難時や事故時の使用が真っ先に思い浮かびますが、自然災害による水没の場合も適用されるので、昨今の異常気象による災害の発生頻度に照らせば、車両保険に加入しておいて損はないように思います。私も自動車については、車両保険に加入しています。
一方、そもそも任意保険に加入してない方、任意保険には加入しているものの車両保険をつけていない方は、保険で水没による損害を補填できませんので、残念ながら、自己負担で修理するか買い替えるほかないと思います。
それにしても、地下駐車場には上記のように大雨の際の水没のリスクがあることを改めて認識しました。浸水対策を施すにしても限度があると思いますので、大雨が降る可能性の高いエリアにお住まいの方は、多少不便でもタワー式駐車場を契約されてもよいかもしれません。
※ 9月29日加筆
上記について、某駐車場では、数年前に浸水防止装置が故障したままになっていたとの報道を目にしました。これが事実であるとすれば、水没車の所有者らは、浸水防止装置を作動させなかった不作為を理由に、当該駐車場の管理者に対して、損害賠償を求める余地があると思われます。ただし、当該浸水防止装置を正常に作動させたとしても、今回の浸水を防げなかったとなった場合には(大雨・洪水が想定を予測不可能な程度であったと認定された場合には)、賠償請求は認められないということになると思います。
2025年9月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
9月に入りました。
今年の夏は猛暑日が続いており、ほとんど出かけることなく室内で過ごすことが多かったと思います。あまりの暑さに、バイクに乗ることも躊躇する状況で、バイクのバッテリー上がりを心配するほどの頻度でしか乗れませんでした。
そういえば、最近、Xで80期あたりから弁護士業界は売り手市場から買い手市場に転じるのではないかという投稿と同投稿が引用するブログを目にしました。確かに、ここ数年は完全な売り手市場であると実感しており、その原因として、弁護士業界の人手不足の背景にあるインハウスロイヤー(企業内弁護士)への転向の増加があるのではないかと個人的に考えていました。企業内弁護士は、10年前と比べて3倍に増加し、現在は約3500人くらい存在するようです。企業の福利厚生の充実度や働きやすさという点に照らせば、共働きが増えつつある現在において、企業への就職を希望する弁護士も増えるのは納得です。また、企業にとっても、少子高齢化による人手不足に悩んでいるところが多いので、企業内弁護士を積極的に採用する傾向にある(企業内弁護士の需要が拡大している)と思います。
そもそも、いわゆる街弁業務(大手企業を対象とした企業法務や渉外業務については私自身が詳しくわかっていませんので、以下では、街弁業務を対象に意見を述べます。)は、個人間の争いに代理人として介入することがメインであり、相応のストレスがありますし(企業内弁護士のストレスが低いといっているわけではありませんので、あしからず。)、急を要する案件の依頼があった場合には、プライベートよりも仕事を優先せざるを得ないことも少なくありませんので、働きやすさという点では、どうしても一般企業の業務に比べて劣るかもしれません。特に、弁護士数が少ない事務所の場合、自身が休んでしまうと自身の担当案件を他の弁護士に任せづらく、業務が停滞してしまいやすいので、責任感のある人ほど無理をして働いてしまうという状況が生じやすいと思います。
ただ、一方で、定時出勤・定時退勤という縛りは強くなく、比較的自由に働けるという大きなメリットがあります(自ら事務所を開設する場合やパートナーとして事務所に参画する場合、自由度はさらに高まります)。また、勤務弁護士として働く場合、個人受任が認められていることが多く、自分の頑張り次第で稼ぎを増やすことができる(仕事量を調整できる)というメリットもあります(企業内弁護士の場合、個人受任を認めている会社はほとんどないのではないかと思っています。)。そのため、個人的には、街弁として働くことにも大きな魅力があると思っており、福利厚生を手厚くする、勤務形態を柔軟に変更する(在宅ワークを積極的に導入する)といった対応をとることにより、街弁業務の人気を少しは復活できるのではないかと思っています。
しかし、いかんともし難いのは、弁護士の都市部集中(新人の都会志向)でしょう。ここ数年、弁護士の求人を出している側として感じるのは、東京や大阪といった都市部にある事務所(本店、支店)への応募は一定数あるものの、それ以外の場所(当事務所でいえば、熊本、仙台)への応募は大変少なく、都市部以外での採用は本当に厳しいということです。この点について、弁護士数が少ないエリアで働いた方が、弁護士数が過剰な都市部で働く場合と比較して、法律相談センターの法律相談に入れる頻度や国選の割り当て数が多くなるので、必然的に個人受任事件の件数も増えますし(収入を増やせますし)、家賃や駐車場代も安価なので、余暇に費やすお金を確保しやすいはずですが、そういった点は事務所選択にあたってあまり重視されていないようです。ほかにも、都市部以外のエリア(弁護士数が少ないエリア)においては、委員会活動等を通じて他の弁護士とのつながりを強く持ちやすいので、先輩弁護士から手厚い指導を受ける機会に恵まれていますし、都市部のように弁護士業務が細分化されていませんので(専門型、ブティック型の事務所は少ないので)、いろいろな事件を担当する機会が豊富にあるというメリットもあるはずですが、これらの点もあまり重視されないようです。
私も昔は都会に強くあこがれて一橋大学に進学したので(東大は私にとってハードルが高かったのです…)、あれこれと偉そうにいうことはできませんが、確かに、若い頃って漠然と都会にあこがれてしまうんですよね…。特に、弁護士の場合、年数を重ねていくことで人とのつながりや顧客が増えていきますので、簡単に事務所移転できない(転勤できない)という事情もあると思います。そのため、最初の事務所選びにあたっては、どの都道府県にある事務所の中から選ぶのかという点は重要であり、規模の大きな都市を魅力に感じて志望する人は多いと思います。転勤があるという条件では、新人弁護士の確保はさらに難しくなるのが実情です。
本題に戻りますが、80期あたりから買い手市場になるのではという予想の背景には、AIの進化による業務の変化(生産性の向上)や期日のウェブ化の普及による効率化といった事情があるようです。
確かに、期日のウェブ化は現時点においてもかなり普及していて、出廷する手間が不要になった分、時間を確保しやすくなりました。また、このようにウェブ化が普及していければ、東京都内にあっても、札幌や長崎といった遠方のエリアの事件も担当しやすくなり、各エリアに支店を設ける必要性は低下しつつあるのではと思います。
しかし、街弁業務に限っていえば、AIによる業務の代替性は高くなく、AIが普及しても需要は減少しないのではないかと思っています。契約書の作成等についてはAIの進化によって、弁護士に依頼する必要性は減少していくと思いますが、個人間の紛争解決をAIで代替することはできないと思います。人は合理性のみで意思決定をするものではなく、感情が意思決定に大きく影響しますので、どれほどAIが普及しても、代理人弁護士を立てて交渉することの必要性はなくならないというのが私の考えです。
ということで、街弁業務については、今後も売り手市場が続くのではないかと思っていますが、企業内弁護士や企業法務分野における弁護士需要が低下し、それらの弁護士求人数が低下することの反射的効果として、街弁事務所への応募が増えて売り手市場が徐々に解消する可能性はあるかもしれません。
ちなみに、私は61期ですが、その当時はすさまじい買い手市場でした。当時、故郷である京都市内での就職を希望していたのですが、公に弁護士求人を出していた事務所はほぼなかったため、京都市内での就職は諦めて、比較的たくさんの求人が出ていた東京都内で勤務先を探し、なんとか採用してもらって今に至っています。京都市内の事務所に入所できていたら、今頃どうなっていたんだろうとふと思ったりしますが、「人間万事塞翁が馬」ということわざのとおり、結果として楽しい日々を過ごせていますので、人生わからないものですね。
2025年9月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
あやうく交通事故に‥
昨日は、顧問先の先生の某発表会にお招きいただいて、SR500というバイクで会場に向かいました。
SR500は、1999年を最後に生産終了となったヤマハのバイクであり、500CCの単気筒でほどよい振動を味わえるのが魅力です。SR400も並行して販売されていましたが、こちらは、数年前まで国内でも販売されていました。中型自動二輪免許で乗れることからSR400は大人気のバイクといえます。一方、SR500に乗るには、大型自動二輪免許を取得しないといけませんが、大型免許をとったなら、もっと排気量の大きいバイクに乗りたいという人が多数派のようで(私もそのタイプです)、SR500は人気の車種とはいえませんでした(あまり売れなかったというわけです)。
ですが、発売中止になったことで稀少性が高まっており、現在の中古車価格帯は、SR400よりも高くなっています。こういった発売当初は不人気だったのに、生産中止後に値段が上がるバイクは珍しいのですが、GS1200SS(スズキが考えたキャチコピーは「男のバイク」でした。カッコよくて、しびれますねww)なんかはその典型例ですね(実は、このバイクも所持していまして、大切に乗っています)。
今後、SR500の中古車価格帯が上がっていくのか、それとも、現状にとどまるのかは不明ですが、私はもう少し乗り続けようと思っています。エンジンが暖まっていない状態では、信号待ちしていたらエンジンが止まることがよくあり、焦ることも多いのですが(普通のバイクと違ってセルがついておらず、キックスタートのみですので、余計に焦ります)、まぁ、そういった点を考慮してもなお、気軽に楽しく乗れるという魅力があります。
さて、ここから本題ですが、昨日、片側三車線の道路の真ん中をバイクで走行していたところ、私の前を走っていた車の前に、左側車線から急に車が割り込んできたことで、私の前の車が急ブレーキを踏んで停止しました。私もこれにあわせて、急ブレーキを踏んだのですが、SR500は最新のバイクとは異なり、ABSがついていないので、後輪がロックして激しくスリップしました。転倒しなかったことが不思議なくらいで、運がよかったとしかいえません。車間距離が不十分だったら、急停止した前の車への衝突を避けられなかったと思います。本当に久しぶりに怖い思いをしました。
ということで、古いバイクに乗っている方には、ABSがついていないことを忘れず、十分な車間距離をとって運転することをお勧めしたいと思います。
ちなみに、上記の事故態様で私が追突していた場合の過失割合はどうなるのかと、ふと考えました。こういった3台が関係する事故の場合の過失割合の算定は容易ではありませんが、左側から急に割り込んできた車と追突した私に過失が認定される可能性はとても高いと思います。問題は、その過失割合ですが、この判断は難しいですね。別冊判例タイムズ38という過失割合算定の基準となる書籍には、こういった態様の事故のケースは掲載されていませんので、過去の裁判例等を調査して推測していくことになろうかと思います。
ただ、今は、その調査の時間をとることはできないので、このブログでは過失割合を記載することはいたしません。その時間があるなら、早く起案してくれというクライアントの声が聞こえてきそうですので‥ww
2025年7月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
医師、歯科医師の応召義務
7月も後半になりました。今月、45歳の誕生日を迎えて肉体的な衰えを日々感じているので、これまで以上に健康には気をつけて過ごしていきたいと思います。
さて、弊所の顧問先には、クリニックや歯科医院が複数あり、時折、応召義務について質問を受けることがありますので、ここで簡単に説明したいと思います。
応召義務については、医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項がそれぞれ下記のように定めています。
医師法第19条1項
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
歯科医師法第19条1項
「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
※ なお、薬剤師法第21条には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合に は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあり、また、保健師助産師看護師法第39条1項にも「業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあります。これらも上記の応召義務と類似した規定ですが、このブログでは説明を省きます。
医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項を素直に解釈すれば、原則として、患者から診療の求めがあった場合には、診療しなければならないが、正当な事由がある場合には例外的に診療を拒否できるということになります。
それでは、上記にいう「正当な事由」にはどのような事情が当てはまるのでしょうか。
この点については、厚生労働省が令和元年12月25日に公表した「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発1225第4号)が大変参考になります。
上記においては、応召義務に反するか否かの判断においては、「患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」が最も重要な考慮要素であると明記されています。
また、診療を求められたのが診療時間・勤務時間内かどうか、患者と医師・歯科医師の信頼関係も次に重要な考慮要素であるとされています。
詳細に記載することは控えますが、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間内である場合には、医師や歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下における医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性等を総合的に勘案して、事実上診療が不可能といえる場合でない限り、診療しなければならないということになります。一方、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間外である場合には、応急的に必要な処置をとることが望ましいものの、診療を拒否しても原則として公法上・司法上の責任に問われることはない(応召義務違反にならない)とされています。
では、緊急対応が必要でない事案の場合はどうなるのでしょうか。
この場合であっても、診療を求められたのが診療時間内である場合には、原則として患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要があるとされていますが、正当な事由の有無は、上述した医師や歯科医師の専門性・診察能力、医療提供の可能性、設備状況等のみならず、患者と医師・歯科医師の信頼関係も考慮して判断されることとなり、かつ、緊急対応が必要な事案である場合と比較して、その判断(解釈)は緩やかになされるとされています。
当然、診療を求められたのが診療時間外である場合には、診療を拒否しても応召義務違反にはならないということになります。緊急性がない以上、このような判断は妥当でしょう。
その上で、緊急対応が必要でなく、かつ、診療時間内の場合であっても、患者の迷惑行為が認められるケース(暴言、暴行、理不尽かつ執拗なクレーム等)、「悪意」による医療費の不払いが認められるケース(なお、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合は悪意のある未払いであると推定される場合もあります。)、医学的に入院の継続が必要ないケース、病状に照らして他院への通院(転院)が相当なケース、言語が通じない、宗教上の理由等によって結果として診療行為そのものが著しく困難になるケース(ただし、単に患者の年齢や性別、人種、国籍、宗教等のみを理由とする場合を除く)等は、診療を拒否できる正当な事由があると判断される可能性があるとされています。
以上、厚生労働省の見解に沿って説明してきましたが、緊急対応が必要でない事案において、応召義務が問題となるのは、主として患者と医師・歯科医師の信頼関係に関するものが多いと感じています。
基本的には、医師・歯科医師は、患者に対して説明義務を負っていますので、同説明義務に基づき、できるだけ丁寧に説明することを心がけて患者との信頼関係を構築すれば、トラブルになることは少ないと思いますが(説明が足りないと、患者が不安に思い、不満も募るのはやむを得ないでしょう。)、中には、何度説明しても納得せず、暴言を繰り返す、何度も同じ説明を求めて長時間にわたって医師・歯科医師を事実上拘束する、医師・歯科医師の指示に従わずに理不尽な要求を繰り返すといった人も残念ながら一定数存在します。このような場合には、他の患者に与える影響等に照らして、診察を拒否することもやむを得ないと考えますが、その場合であっても、例えば、「これ以上、暴言を吐くなら、信頼関係を維持できないので、診療できなくなる」等と伝えて、事前に予告(注意)しておくのが無難と思います。突然、診療を拒否すると、トラブルに発展しやすいので、この事前の予告(注意)は重要です。
2025年7月22日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学