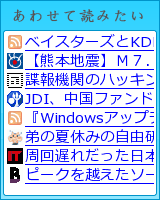改正法科大学院法
梅雨入りして蒸し暑い日が続いていますね。暑さで喉が渇きやすくなっているせいか、3日連続で事務所近くにあるタピオカの店「コンマティー恵比寿店」に立ち寄って、タピオカミルクティー飲んでいます。若い女性が多く並んでいると中年オヤジの私がその列に並ぶのはちょっとはばかられるのですが、平日日中はわりと空いており、並ばずに購入できるのがありがたいです。
さて、昨日ニュースで報道されていますが、改正法科大学院法が参議院にて可決され、成立しましたね。これまでは法科大学院を卒業するか予備試験に合格しないと司法試験を受験できなかったのですが、一定の要件を満たせば法科大学院の最終学年在学中に司法試験を受験できるようになるようです。
法科大学院生にとっては、これほど嬉しいことはないですね。もっと早くこのように改正すべきだったのにと思ってしまいますが。
現状、法科大学院受験者数が減少傾向にある一方で、予備試験受験者数は増加傾向にあるため、法科大学院受験者数を増加させる目的があるのではと思っています。予備試験に合格さえすれば、法科大学院を卒業しなくても司法試験を受験できますので、大学在学中に予備試験受験→司法試験受験というのが法曹になる最短ルートである一方、法科大学院ルートは大学学部卒業(場合によっては飛び級入学)→法科大学院卒業→司法試験受験というプロセスを経なければならず、一定の年数がかかる上に法科大学院の学費もかかるため、予備試験ルートで司法試験合格を目指すのが合理的というほかなく、上記のような傾向になることはやむをえないというほかありません。
この度の改正によって、多少は法科大学院受験者数が増えると思いますが、それでも、予備試験ルートの方が時間も費用もかからないので、予備試験受験者数が大きく減少することはないと思います。
受験者数減少に苦しみ、生徒が集まらなくて廃校となる法科大学院は今後も発生すると思います。
2019年6月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
残業代請求権の消滅時効改正
東京もとうとう梅雨入りしたせいか、連日天候がよくなくて、バイクに乗れずに
います。長期間バイクに乗らないとバッテリーが上がって動かなくなってしまう上に、いったん上がったバッテリーは充電しても完全には回復しないので、梅雨の季節は真冬と同様に、バイク乗りにとって厳しいというほかありません。バッテリーが上がらないことをひたすら祈る毎日です(笑)。
さて、そんな中、2020年4月1日施行予定の改正民法にあわせて、労働基準法も改正されるのでは?というニュースを目にしました。
今回の改正民法では、消滅時効期間が「権利を行使できるときから5年」となるようですが、それにあわせて賃金債権の消滅時効期間も「5年」に改正される見通しとのことでした(ちなみに、現行法上、賃金債権の消滅時効期間は「2年」です。)。
仮に、上記のように賃金債権の消滅時効期間が「5年」に改正された場合、労働者から使用者に対する残業代請求の金額が大幅に増大されることになり、労働者にとっては喜ばしいニュースだと思います。他方で、使用者にとっては厳しいニュースであることは言うまでもなく、使用者はこれまで以上にしっかりと労務管理を行わなければならなくなります。
改正後は、改正前と比べて、残業代請求事件の件数は間違いなく増加するでしょうね。
2019年6月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
令和元年司法試験
仕事の合間に弁護士ブログを読んでいたら、今日から5月19日まで司法試験が実施予定と知りました。記念すべき令和元年の司法試験ですね。
私が受験したのは平成19年だったと思いますので、10年以上前になります。あれから、試験の内容そのものもいろいろと変更になりました。平成19年当時は、択一試験は基本六法+行政法だったのですが、今は旧司法試験と同じく憲法・民法・刑法の3科目だけになっています。また、平成19年当時の論文試験は、公法系・民事系・刑事系に大きく分かれ、各分野の融合問題を出題するという内容だったため、公法系と刑事系は確か4時間連続の試験だったと思います。他方で、民事系はさすがに6時間連続はキツイだろういう配慮から?民法と民事訴訟法で4時間、商法で2時間だったと思います。しかし、今は、各科目2時間ずつとなっていますね。この点も旧司法試験と同様です(旧司法試験は各科目2時間で2問ずつ出題されていました。)。
そうなると、出題形式(問題文が長い、事実認定がある等)の点の違いを除けば、新司法試験は旧司法試験に戻っているように思います。そうなると、あえて新司法試験とせずとも、旧司法試験のままで合格者数を増やせばよかったんじゃないか?なんてツッコミが入りそうですね。まぁ、受験回数制限の有無が最大の違いでしょうけども(旧司法試験には受験回数制限はありませんでした)。
いずれにせよ、今年の受験生の皆さん、最後まで頑張ってください。今の試験に通用するかどうかわかりませんが、私の経験上、普段と異なることをしないこと、途中答案を出さないこと、問題文の誘導にきちんとのっかること(問題文を読み間違えないこと)、論述にメリハリをつけること(些細な争点で法律論を大展開する等の方法は控えるべきでしょう。)、試験が終わった科目のことは忘れること等の点に気をつければ、それだけで相対的によい答案になると思います。
(私自身は、恥ずかしながら、途中答案に近い答案を出し、最初の科目で失敗して後に引きずり、普段と異なって自分の書くスピードを度外視してたくさん書こうとして時間不足になり、問題文を読み落とすという失敗をしてしまいましたが、それでも合格できましたので、大きなミスをしなければ落ちないという程度の気持ちでリラックスして受験するのがよいと思います。)
2019年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
民事執行法の改正
令和最初のブログは真面目に法律的なニュースに言及いたします。
標題のとおり、改正民事執行法が本日成立したようです。施行は1年以内。
改正によって、子の引き渡しの執行方法が明確になった上に(ちょっとわかりにくいかもしれませんが、一方の親が現場にいなくても、引き取る側の親がいれば、執行官が子どもを強制的に引き渡すことができるようになったようです。)、財産開示の手続きが新たに整備されたようです。
具体的な改正法案をまだ見ていないので詳細は不明ですが、インターネット上の情報を見るかぎり、裁判所を通じて、市町村や銀行本店等に問い合わせることで勤務先や銀行の支店の預金口座の有無を知ることができるようになるとのことです。
今回の改正によって、いわゆる「逃げ得」はかなり減るのではないでしょうか。一般論ですが、弁護士は、勤務先や財産状況がわからず、判決を取得しても金員を回収できない可能性が高いと思われる案件については、特段の事情がない限り、受任を躊躇するのですが、上記改正民事執行法によって、そういう案件でも積極的に対応できるようになると思います。
2019年5月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
平成最後のブログ更新
とうとう明日から元号は令和となりますね。私は昭和の生まれですが、平成元年(昭和64年)のころはまだ小学生でした。当時、携帯電話やパソコン、インターネットがほぼ普及していなかったことに鑑みると、平成の30年間でずいぶんと世の中は便利になったものだとしみじみ感じます。
法曹界にかぎっていえば、平成元年前後の話か否かは定かではありませんが、手書きで訴状や準備書面を作成していた時代があったようです。確かに、これらの書面を手書きで作成するとなれば、その苦労は想像を絶するものがありますね。特に、私は字が綺麗ではありませんので、私が手書きで作成した場合、それを読む相手方は大変なストレスを抱えるのではと思ってしまいます(笑)今でも、本人訴訟の場合等には手書きで書面を提出される方はたくさんおられますが、弁護士が代理人となっている事件では、手書きで提出される書面はほぼ見かけなくなりました。
その他、平成の時代に民法や商法(会社法)が改正されて、カタカナ表記からひらがな表記に変わったことも大きな出来事だと思います。私が大学生のときはどちらもカタカナ表記でしたので、条文を読みにくいと感じていました。
私が弁護士登録したのは平成20年12月であり、平成31年までの約10年間で法曹界で何か変わったことってあるのかなとこの機会に思い返してみました。うーん、殺人罪等の重大事件の公訴時効制度の廃止や強姦罪が強制性交等罪に変更されたこと(強姦罪の被害者は女性に限定されており、男性を被害者とする強姦罪は成立しないとされていましたが、強制性交等罪に変更されたことで男性もこの罪の被害者となりうることが明確にされました。)等の法改正ばかりが思い起こされますが、ほかには目新しい動きはなかったような…。あとは、法曹志望者(司法試験受験者)の数が劇的に減少したことやいくつもの法科大学院が廃止されたことくらいでしょうか。
あぁ、そういえば、法律事務所の大半がホームページを開設するようになったことも大きな変化ですね。私が弁護士に登録したての頃は、ホームページを開設している法律事務所はまだまだ少数派でした。最近は、ホームページを開設して積極的に集客している事務所がたくさんあります。その意味で、法律事務所の敷居は低くなり、相談者にとって利用しやすいものになったのではと思います。
以上、とりとめのないことばかり書いてきましたが、令和の時代には、法曹界のIT化が進むことを期待して、今日は筆をおきます。それでは、皆さま、引き続き、よきGWをお過ごしください。
2019年4月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
交通事故に遭ったら
今年も桜の季節がやってきました。私は、自宅から事務所(恵比寿)までバスで通勤することが多いのですが、その間、明治通りの桜が咲き誇る場所を通過します。通勤途中にこの桜を見て、人知れず心癒されています。桜といえば、恵比寿近辺だと中目黒の目黒川沿いの桜が有名ですが、毎年多くの人がきて混雑しますので、ここ数年は明治通りの桜を見て満足しています。
さて、弊所では、交通事故相談も多数受けているのですが、今回は、交通事故に遭った場合に知っておいた方がよい知識を簡単にお伝えできればと思います。
まず、交通事故に遭ったら、その場で警察と保険会社に連絡することが重要であることは言うまでもありません。その際、怪我をしていたら、可及的速やかに病院に行って診てもらうこと、警察に人身事故扱いとしてもらうことも同様に重要です。
後日、痛みを感じて病院に行った場合や痛みがあっても我慢していて仕事をし、痛みに耐えきれなくなって病院に行った場合には、怪我と交通事故との因果関係を認めてもらえないおそれがあります(交通事故に遭った日から病院に初めて行った日までに、どの程度の期間が経過しているかが重要な判断要素となります)。
また、事故で発生した自動車・自転車の損傷個所や怪我の部位の写真を撮っておくことや、事故の相手方の名前や連絡先を確認して記録すること(名刺をもらうこと等)も重要です。
その上で、一般的にあまり知られていないことですが、接骨院や整骨院(柔道整復師が施術を行うところ)と整形外科は異なり、接骨院や整骨院にしか通院していない場合には、事故の相手方の保険会社から施術費用の支払いを拒否されるおそれがあります。接骨院や整骨院は、医師の同意のもとで通院することが望ましく、整形外科と接骨院・整骨院を並行して通院することをお勧めします。整形外科には最低でも月に1回は通院した方がよいです。
通院にあたっては、痛い箇所を明確に漏らさず伝えましょう。最初に伝えていなかったところを後から伝えて治療・施術してもらっても、交通事故との因果関係が不明として費用の支払いを拒否されるおそれがあるためです。
怪我が完治したら通院終了となりますが、そうなると事故の相手方の保険会社から示談金の提案がなされます。この示談金は、保険会社独自の基準又は自賠責保険の基準で算定されていることがほとんどで、裁判基準(弁護士基準)よりも低額であることが多いです。そのため、示談金が適切かどうか悩んだ場合(示談金の金額に納得できない場合)や事故の過失割合について納得できない場合には弁護士に相談することを検討してもらうとよいと思います。このとき、ご自身の保険に「弁護士特約」が付いていれば、大きな事故で損害額が多額になる場合を除いて、弁護士費用を自己負担することなく相談・依頼できますので(弁護士特約によって保険会社から支払われます。)、積極的に相談することを検討しましょう。
他方で、怪我が完治せず、「これ以上治療しても治療効果が出ない状態(怪我が改善しない状態)」に至った場合を「症状固定」といい、この場合には後遺障害認定の申請をすることを検討することになります。このとき、後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが必要となりますが、同後遺障害診断書は後遺障害認定にあたって極めて重要なものですので、しっかりと医師に自己の症状を伝えるようにしてください。
なお、交通事故に遭った場合の通院費用は必要かつ相当な範囲に限られ、いわゆる「過剰診療」は認められません。わかりやすい例でいうと、自動車同士の追突事故で、追突時の速度が時速5キロ未満と遅く、自動車の損傷の程度も小さいにもかかわらず、痛みがあるからという理由で長期間通院を続けても、特段の事情がない限り、その期間の通院費用を認めてもらえない可能性が高いといえます。
以上、ざっと書いてきましたが、このブログを見ていただいている方の参考になれば幸いです。
2019年4月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
事務所名を悪用する詐欺
もうすぐ2月も終わりですね。今月は各種の起案に追われていて久々に忙しくしていました。
さて、タイトルのとおりですが、この度、弊所(琥珀法律事務所)の名前を語る詐欺事件が発生しました。
概要は、「ある刑事事件で弁護士を探していたところ、知人から法律事務所の電話番号を教えてもらって、紹介を受けた番号に電話したら、電話の相手が『琥珀法律事務所の弁護士のシイナ』と名乗り、契約書等は不要なので着手金を先に払うよう指示された。その指示に従って、指定の口座に●万円を振込んだ。その後、音信不通となった。」、「その後、インターネットを調べて琥珀法律事務所のホームページを見つけて電話した。」というものでした。上記電話番号について調べたところ、闇金の電話番号のようでした。
弊所には、「シイナ」という名前の弁護士は所属しておりませんし、弊所のホームページ上に掲載されている電話番号以外に対外的な電話番号はありません。上記の案件は、弊所名を悪用する詐欺でした。
弁護士は委任契約を締結するにあたって契約書を作成しなければなりませんし、着手金や報酬金についても明確に説明しなければなりません。面談もしない段階で、先に着手金を支払うように指示することは、よほどの緊急案件でやむを得ない事情がある場合を除き、ありません。また、着手金や預り金をお振込みいただく口座の名義には、「●●法律事務所」、「弁護士●●」、「●●法律事務所預り金口」という言葉が入っています。このことを弁護士に依頼される皆様には覚えておいていただければと存じます。
上記のような「とにかく先にお金を振り込んで」という指示を受けた場合には、間違いなく怪しいです。最近では、弊所を含め、ほとんどの法律事務所にホームページがありますが、事務所所属の弁護士や電話番号は、事務所のホームページや日弁連のホームページにある弁護士検索を調べれば判明しますので、紹介を受けた場合には、事前にそれを確認することを徹底してもらえればと思います。
今回、どうして弊所の名前が語られたのかわかりませんが、弊所のみならず、他の法律事務所名を悪用する詐欺は他にもたくさんあると思いますので、相談者の皆さまには気をつけてもらえればと思います。
2019年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
新年のご挨拶
皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年12月24日付のブログでも少し触れましたが、今年一年は琥珀法律事務所の本店と各支店を行き来することが増えそうです。1年の3分の1から半分くらいは東京にいないかもしれません。
弁護士になってから10年が経過しましたが、その間、ほぼ東京にいましたので、今年は自分にとって目新しい一年となると思っています。せっかくなので、各支店に滞在している間は、空いた時間を利用して各地域の観光スポット巡りをしようかとか、バイクで各地のツーリングスポットを巡ろうかとか、いろいろと想像を膨らませています。
あとは、今年こそ、健康維持のために、ゴルフ以外に何らかの運動を始めようと思っています。気軽に始められるのはランニングだと思いますが、あっという間に飽きて続かなくなりそうなので、他に何かないか、じっくり探したいと思います。トレッキングとか楽しそうですね。
ということで、とりとめのない話をダラダラと展開して恐縮ですが、今日はこのへんで。
皆様にとってもこの1年が実り多き年となるようお祈り申し上げます。
2019年1月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
平成最後のクリスマスイブの夜に
何しているかって? 数日前から立て続けに入った相談の調査を黙々と事務所で行っております。事務所の電話がほとんど鳴らないため、けっこう集中できますね。同業者ならご理解いただけると思います、この気持ちを。
そういえば、今年のクリスマスシーズンである12月22日~24日が三連休なため、街に出て夜を楽しんでいる方々が多いように感じました。
昨日もけっこう遅い時間なのに、恵比寿駅周辺にはたくさん人がいて賑わっていました。こういうのを見ると寂しく感じたりもするのですが、それは私にパリピ(パーリーピーポー)の素質があるからでしょうかね(笑)。
今年も残すところ、わずかとなりました。当事務所は平成30年12月29日から平成31年1月3日までお休みとなり(支店によっては29日まで営業しています。)、基本的にその間、事務所の電話は留守電となりますので、ご了承ください。なお、顧問先の皆様におかれましては、万が一、突発的なトラブル等に巻き込まれた場合には、私の業務用携帯電話あてにご連絡いただければと存じます。可能な限り対応させていただきます。
今年一年を振り返ってみると、従前と同様にいろいろなことがありましたが、なんとか1年を乗り切ることができてひとまず安心しています。まぁ、不安材料が全て解消したわけではなく、年明けからテコ入れしないといけないので、まだまだ落ち着ける状態にないんですけども。
来年は、既存の支店の補強と新たな支店の開設、それによる「より良いリーガルサービスの提供」を目標に頑張りたいと思います。
最後に、今度の年末年始は、法律書、雑誌、マンガ等のジャンルを問わず好きな本を好きなだけ読んで、ストレス解消&法律・経営の知識補充に努めたいと思います。私は読書がけっこう好きなので、ゆっくり本を読める年末年始はけっこう幸せなんです。
それでは、皆さま、よいお年を。
2018年12月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
71期二回試験
昨日は、司法修習生が弁護士・裁判官・検察官になるための登竜門、通称「二回試験」(司法研修所の卒業試験。司法試験から数えて2つ目の試験なので「二回試験」と呼ばれています。)の合格発表でした。
今年は、不合格者が16名だったとのことですので、よほど大きなミスをしない限り合格できたのではないかと思います。受験者数が約1500人ですから不合格率は1パーセント程度だと思います。
こうなると、周囲からは「99パーセントも合格できるのだから余裕だろう」と思われるかもしれませんが、だからこそ、プレッシャーはものすごいものがあります。「1パーセントの中に入ったらどうしよう」、「不合格だった場合、周囲からどう思われるんだろう」っていう恐怖感はなかなか大きいものです(少なくとも、私が受験したとき、私はそう思っていて怖かったです。)。72期の司法修習生のみなさんにはプレッシャーに負けることなく頑張ってほしいと思います。
二回試験の合格発表の季節になると、私自身の体験を思い出してしまいます。私の場合、初日の試験科目である民事裁判において、大失敗をしてしまったため、不合格間違いなしと思っていました。初日の失敗によって意気消沈し、その後の4科目(刑事裁判、刑事弁護、民事弁護、検察)については「どうとでもなれ」という投げやりな気持ちで全く緊張することなく受験したことをよく覚えています。リラックス?して受験できたので、よかったのかもしれません。
結果として、合格していたのですが、我ながら「よく合格できたな。」というのが率直な感想でした。私が受験したときは、不合格者数は101名、不合格率は5パーセント強でした。検察科目による不合格者が多かったと記憶しています。
私の場合、受験が終わってから合格発表までの間に、翌年の二回試験までどうやって過ごそうかといろいろ悩みました。憂鬱だったため、同期の修習生らとの卒業旅行にも行けませんでした。
今年不合格となった修習生についても、来年度の二回試験までの過ごし方について同じようにいろいろと悩まれるかもしれません。もしかしたら、内定先から内定取り消しを受けるかもしれませんし、そのまま内定先で事務員として雇ってもらえるかもしれません。しかし、いずれにせよ、今年の試験のミスを分析した上で、不合格となった修習生同士で密に連絡を取り合い、来年度の試験までモチベーションを維持することが何より重要だと思います。
二回試験に落ちても来年度合格すればよく、合格した修習生に比べて弁護士になるのが1年遅れたとしても、その後の努力次第で容易に追い抜けます。ということで、今年不合格だった修習生のみなさんには、早く気持ちを切り替えて、頑張ってほしいと思います。
2018年12月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記