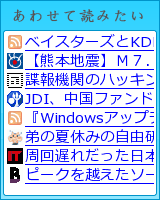令和7年度貸金業務取扱主任者試験
昨日、今年初の資格試験である貸金業務取扱主任者試験を受験してきました。貸金業者は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数が1:50以上の割合となるように貸金業務取扱主任者を置かなければなりませんので、貸金業を行う者にとっては重要な資格です。
そのため、今後、貸金業を行う予定のない(現時点で貸金業社に入社する予定のない)私にとっては不要な資格ということになりますが、琥珀法律事務所では交通事故事件・労働事件と並んで債務整理事件も多数取り扱っているので、貸金業法や利息制限法をこの機会により深く勉強しようと思って、受験を決意したのです。実際、勉強を通じて、貸金業法、利息制限法(特に貸金業法)の条文に詳しくなりましたし、貸金業者向けのガイドラインも学んで、犯罪収益移転防止法や個人情報保護法等の他の法律も復習することができました。
貸金業務取扱主任者試験の合格率は毎年30パーセント前後ですので、宅建試験(合格率15~18パーセント程度)に比べると易しいといえます。実際、過去問5年分に目を通しましたが(全部解くことは時間的に無理でしたが、それなりに解答・解説を読み込みました。)、宅建やマンション管理士試験(合格率7~8パーセント程度)に比べて、素直な問題が多く、内容も平易で取り組みやすいと感じました。
で、昨日の試験の出来についてですが、意外にも、想像していた以上に難しく感じ、けっこう苦戦しました。当日の試験開始直前まで過去問題集に目を通し、合格はできるかなと一定の自信をもっていたのですが、いざ試験が始まると初見の選択肢がいくつもあって焦りましたね。絶対時間が余ると思っていたのに、実際には2時間フルに使って50問を解き終えました。これが試験の怖いところですね。
で、各種予備校が出す解答速報を心待ちにしていたのですが、貸金業務取扱主任者試験については、受験者数が宅建等に比べて少ないためか、試験当日に解答速報は出されず、TACが11月18日17時に発表する解答速報が最短のようでした。
ということで、気になる私は、試験後に事務所で1件相談業務に対応した後に帰宅し、そこから解答を調べました。以下、私なりに調べた解答ですが、全て合っているかどうかは自信がありません(責任をおいかねます)。このブログを見た貸金業務取扱主任者試験受験者の方は、明日のTACの発表と照らし合わせてもらえればと思います。
14224 14322 41332(12問目は1ではなく2かも?)
23123 42314 41332
41142 33434 24323 41122
ちなみに、自己採点では私の点数は30点台後半でした。それなりに勉強したのに財務及び会計に関することの問題(48~50問)を全部間違えてしまった上に、民法の問題も2問間違てしまって(根抵当権の問題と期限・期間の問題)、もっと勉強しないといけないと改めて思いました。受験前は40点以上とると意気込んでいたので、やや残念に思いますが、試験自体はマークミスがない限り(又は上記解答例が間違っていない限り)、合格できていると思いますので、結果オーライかなと考えて、次の試験に向けて勉強を開始します。
タグ
2025年11月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
通常逮捕の要件
今月も3分の1を経過しました。今年もあと2か月弱ですが、インフルエンザが世間で流行っていますので、体調管理に気をつけて過ごしていきたいと思います。
さて、昨日、N国党の立花孝志氏が名誉毀損の被疑事実により通常逮捕されたとの報道がありました。この逮捕について、逮捕の必要性があったのかという点が問題として取り上げられており、X等で投稿が繰り返されています。そのため、参考までに、このブログでも簡単に説明しようと思います。
通常逮捕については、刑事訴訟法199条1項本文が「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と定めています。この規定の仕方に照らせば、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」さえあれば、逮捕状の発付を受けて通常逮捕が可能なように読めますね。
しかし、199条1項但し書きは、上記本文について、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく、出頭の求めに応じない場合に限ると定めています。また、199条2項は、裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官等の請求に応じて逮捕状を発すると定める一方で、同条2項但し書きにおいて、「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とも定めています。
上記の条文構造に照らせば、逮捕状の発付にあたっては、逮捕の必要性があることを要件と解することができ、199条1項但し書きが30万円以下の罰金等に当たる軽微な犯罪について、住居不定や任意の呼び出し不出頭を要件としているのは、軽微な犯罪の場合には類型的に逮捕の必要性が認められにくい(小さい)と捉えているためと考えられます。
※ 罰金に処されることをおそれて逃亡を図ったり、証拠隠滅を画策する人は少ないでしょう。
また、刑事訴訟規則142条は、逮捕状の請求書に帰しすべき事項を定めていますが、その記載事項の中には「被疑者の逮捕を必要とする事由」が含まれていますし、同規則143条1項は「逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。」と定めていますので、やはり、逮捕の必要性は逮捕状発付の要件と解するのが相当といえます。
そして、逮捕の必要性については、刑事訴訟規則143条の3が「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と定めていますので、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの有無・程度が逮捕の必要性の有無の判断において重要であると推測されます。
※ 勾留の要件である勾留の必要性の有無の判断と同様に、身柄拘束の必要性(証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等)と身柄拘束によって被疑者が被る不利益を比較衡量して、前者が後者を上回る場合には逮捕の必要性があると判断するのが学界の多数説ではないかと思います。
以上を前提として、立花氏の通常逮捕について、逮捕の必要性があったかどうかを検討しますと、名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑」(刑法230条)であり、殺人や強盗、放火等の犯罪に比べると、その法定刑は重くありません。
このように、法定刑が比較的軽いもの(殺人等の犯罪のように、有罪となった場合に原則として実刑判決が下るものではなく、略式起訴で罰金刑にとどまったり、拘禁刑に執行猶予が付される可能性が高い犯罪)については、実刑判決をおそれて逃亡する可能性が高いとはいえませんし、わざわざ証拠隠滅を図る可能性も高いとはいえません(あくまで一般論です)。そうすると、立花氏については、逮捕の必要性が否定されるように思えます。
しかし、立花氏には、執行猶予中であるという特殊な事情があります。執行猶予中に罪を犯し、公判請求され裁判で有罪と認定された場合、原則として実刑判決が下りますし、執行猶予が取り消されて、過去の分もあわせて刑務所に服役することになってしまいます(なお、罰金刑に処された場合には執行猶予は取り消されません。)。この不利益は相当大きなものですので、一般的に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると認められやすくなります。
実際に、立花氏が逃亡するかどうかではなく(人柄、性格に照らせば逃亡するような人ではないといった主張はあまり意味をなさず)、立花氏が置かれた状況を客観的にみて、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性を根拠づける事情があると合理的に推認できるかどうかが、逮捕の必要性の有無の判断にあたって重要ということです。
ただし、逮捕に続いて、勾留が認められるかどうかという点については、別途検討が必要になります。勾留が認められると原則として10日間、延長されれば20日間の身柄拘束が認められてしまいます。このように、逮捕に比べて、身柄拘束期間が長期にわたりますので、勾留の要件である、住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれと勾留の必要性は、いずれも厳格に判断すべきとされています(実際には、抽象的なおそれがあるにとどまるのに勾留決定がなされている事案は少なくないように感じますが、それでもなお、逮捕における必要性の有無の判断に比べると厳格に判断されていると思います。)。そのため、立花氏の場合、勾留請求が認められない(裁判官が認めない)可能性は十分あると思いますし、いったん勾留決定がなされても、弁護側が準抗告を申し立てることにより、当該勾留決定の判断が覆る可能性もあるでしょう。
したがって、立花氏の事案においては、勾留決定が出た場合には、ほぼ間違いなく、弁護側が準抗告を申し立てるのではないかと思います。個人的には、逮捕や勾留を安易に認めるべきではないと考えていますので(身柄拘束による不利益は、大多数の人にとって大変大きいものだからです。)、海外逃亡を防ぐべくパスポートを弁護人が預かるといった事情があるならば、勾留は認めるべきではないと考えます。立花氏は日本全国で有名であり、国内逃亡を図ることは極めて困難でしょうから、海外逃亡を防止する措置さえ講じられるのであれば、身柄拘束は不要と思います。過去に、カルロスゴーンがプライベートジェット機で海外逃亡しましたが、これは例外中の例外とみるべきでしょう。
タグ
2025年11月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学