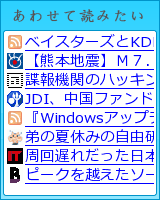医師、歯科医師の応召義務
7月も後半になりました。今月、45歳の誕生日を迎えて肉体的な衰えを日々感じているので、これまで以上に健康には気をつけて過ごしていきたいと思います。
さて、弊所の顧問先には、クリニックや歯科医院が複数あり、時折、応召義務について質問を受けることがありますので、ここで簡単に説明したいと思います。
応召義務については、医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項がそれぞれ下記のように定めています。
医師法第19条1項
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
歯科医師法第19条1項
「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
※ なお、薬剤師法第21条には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合に は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあり、また、保健師助産師看護師法第39条1項にも「業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがあります。これらも上記の応召義務と類似した規定ですが、このブログでは説明を省きます。
医師法第19条1項と歯科医師法第19条1項を素直に解釈すれば、原則として、患者から診療の求めがあった場合には、診療しなければならないが、正当な事由がある場合には例外的に診療を拒否できるということになります。
それでは、上記にいう「正当な事由」にはどのような事情が当てはまるのでしょうか。
この点については、厚生労働省が令和元年12月25日に公表した「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発1225第4号)が大変参考になります。
上記においては、応召義務に反するか否かの判断においては、「患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」が最も重要な考慮要素であると明記されています。
また、診療を求められたのが診療時間・勤務時間内かどうか、患者と医師・歯科医師の信頼関係も次に重要な考慮要素であるとされています。
詳細に記載することは控えますが、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間内である場合には、医師や歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下における医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性等を総合的に勘案して、事実上診療が不可能といえる場合でない限り、診療しなければならないということになります。一方、緊急対応が必要な事案であり、かつ、診療時間外である場合には、応急的に必要な処置をとることが望ましいものの、診療を拒否しても原則として公法上・司法上の責任に問われることはない(応召義務違反にならない)とされています。
では、緊急対応が必要でない事案の場合はどうなるのでしょうか。
この場合であっても、診療を求められたのが診療時間内である場合には、原則として患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要があるとされていますが、正当な事由の有無は、上述した医師や歯科医師の専門性・診察能力、医療提供の可能性、設備状況等のみならず、患者と医師・歯科医師の信頼関係も考慮して判断されることとなり、かつ、緊急対応が必要な事案である場合と比較して、その判断(解釈)は緩やかになされるとされています。
当然、診療を求められたのが診療時間外である場合には、診療を拒否しても応召義務違反にはならないということになります。緊急性がない以上、このような判断は妥当でしょう。
その上で、緊急対応が必要でなく、かつ、診療時間内の場合であっても、患者の迷惑行為が認められるケース(暴言、暴行、理不尽かつ執拗なクレーム等)、「悪意」による医療費の不払いが認められるケース(なお、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合は悪意のある未払いであると推定される場合もあります。)、医学的に入院の継続が必要ないケース、病状に照らして他院への通院(転院)が相当なケース、言語が通じない、宗教上の理由等によって結果として診療行為そのものが著しく困難になるケース(ただし、単に患者の年齢や性別、人種、国籍、宗教等のみを理由とする場合を除く)等は、診療を拒否できる正当な事由があると判断される可能性があるとされています。
以上、厚生労働省の見解に沿って説明してきましたが、緊急対応が必要でない事案において、応召義務が問題となるのは、主として患者と医師・歯科医師の信頼関係に関するものが多いと感じています。
基本的には、医師・歯科医師は、患者に対して説明義務を負っていますので、同説明義務に基づき、できるだけ丁寧に説明することを心がけて患者との信頼関係を構築すれば、トラブルになることは少ないと思いますが(説明が足りないと、患者が不安に思い、不満も募るのはやむを得ないでしょう。)、中には、何度説明しても納得せず、暴言を繰り返す、何度も同じ説明を求めて長時間にわたって医師・歯科医師を事実上拘束する、医師・歯科医師の指示に従わずに理不尽な要求を繰り返すといった人も残念ながら一定数存在します。このような場合には、他の患者に与える影響等に照らして、診察を拒否することもやむを得ないと考えますが、その場合であっても、例えば、「これ以上、暴言を吐くなら、信頼関係を維持できないので、診療できなくなる」等と伝えて、事前に予告(注意)しておくのが無難と思います。突然、診療を拒否すると、トラブルに発展しやすいので、この事前の予告(注意)は重要です。
2025年7月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:法律学