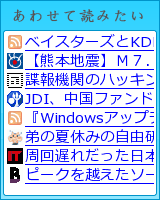大雨による被害
先週はほぼ熊本事務所、福岡事務所で過ごしており、先週土曜の夜に東京に戻ってきました。今日は、昼に面談予定があったので、立川事務所で一日執務しています。
9月も半ばに差し掛かって、ようやく日中の暑さも和らいできたと感じています。
さて、私が九州に出張していた間に、三重県や静岡県、東京あたりで大雨が降って、
地下駐車場がいくつか冠水したというニュースを目にしました。大切な車が水に浸かってしまって、使用不可になるのは精神的にも経済的にも負担が大きいことは当然であり、被害に遭われた方の心中は察するに余りあると思います。
上記のケースでは、車のエンジン部分を超える水位まで水没していた様子が垣間見られました。このように、エンジン部分を超えるところまで水につかってしまうと、全損扱いになることが多いようです(ハイブリッド車や電気自動車は特にそういえます)。
そうすると、買い替えを前提に検討せざるを得なくなるので、被る損害は甚大というほかありませんが、このような自然災害による水没のケースでも、自動車保険(任意保険)に車両保険がついていれば補償の対象となります(ただし、地震・噴火を原因とする津波による浸水を除きます。)。
したがって、まずは、自身が加入する任意保険に車両保険がついているかどうかを確認されるのがよいと思います。車両保険といえば、盗難時や事故時の使用が真っ先に思い浮かびますが、自然災害による水没の場合も適用されるので、昨今の異常気象による災害の発生頻度に照らせば、車両保険に加入しておいて損はないように思います。私も自動車については、車両保険に加入しています。
一方、そもそも任意保険に加入してない方、任意保険には加入しているものの車両保険をつけていない方は、保険で水没による損害を補填できませんので、残念ながら、自己負担で修理するか買い替えるほかないと思います。
それにしても、地下駐車場には上記のように大雨の際の水没のリスクがあることを改めて認識しました。浸水対策を施すにしても限度があると思いますので、大雨が降る可能性の高いエリアにお住まいの方は、多少不便でもタワー式駐車場を契約されてもよいかもしれません。
※ 9月29日加筆
上記について、某駐車場では、数年前に浸水防止装置が故障したままになっていたとの報道を目にしました。これが事実であるとすれば、水没車の所有者らは、浸水防止装置を作動させなかった不作為を理由に、当該駐車場の管理者に対して、損害賠償を求める余地があると思われます。ただし、当該浸水防止装置を正常に作動させたとしても、今回の浸水を防げなかったとなった場合には(大雨・洪水が想定を予測不可能な程度であったと認定された場合には)、賠償請求は認められないということになると思います。
タグ
2025年9月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記
9月に入りました。
今年の夏は猛暑日が続いており、ほとんど出かけることなく室内で過ごすことが多かったと思います。あまりの暑さに、バイクに乗ることも躊躇する状況で、バイクのバッテリー上がりを心配するほどの頻度でしか乗れませんでした。
そういえば、最近、Xで80期あたりから弁護士業界は売り手市場から買い手市場に転じるのではないかという投稿と同投稿が引用するブログを目にしました。確かに、ここ数年は完全な売り手市場であると実感しており、その原因として、弁護士業界の人手不足の背景にあるインハウスロイヤー(企業内弁護士)への転向の増加があるのではないかと個人的に考えていました。企業内弁護士は、10年前と比べて3倍に増加し、現在は約3500人くらい存在するようです。企業の福利厚生の充実度や働きやすさという点に照らせば、共働きが増えつつある現在において、企業への就職を希望する弁護士も増えるのは納得です。また、企業にとっても、少子高齢化による人手不足に悩んでいるところが多いので、企業内弁護士を積極的に採用する傾向にある(企業内弁護士の需要が拡大している)と思います。
そもそも、いわゆる街弁業務(大手企業を対象とした企業法務や渉外業務については私自身が詳しくわかっていませんので、以下では、街弁業務を対象に意見を述べます。)は、個人間の争いに代理人として介入することがメインであり、相応のストレスがありますし(企業内弁護士のストレスが低いといっているわけではありませんので、あしからず。)、急を要する案件の依頼があった場合には、プライベートよりも仕事を優先せざるを得ないことも少なくありませんので、働きやすさという点では、どうしても一般企業の業務に比べて劣るかもしれません。特に、弁護士数が少ない事務所の場合、自身が休んでしまうと自身の担当案件を他の弁護士に任せづらく、業務が停滞してしまいやすいので、責任感のある人ほど無理をして働いてしまうという状況が生じやすいと思います。
ただ、一方で、定時出勤・定時退勤という縛りは強くなく、比較的自由に働けるという大きなメリットがあります(自ら事務所を開設する場合やパートナーとして事務所に参画する場合、自由度はさらに高まります)。また、勤務弁護士として働く場合、個人受任が認められていることが多く、自分の頑張り次第で稼ぎを増やすことができる(仕事量を調整できる)というメリットもあります(企業内弁護士の場合、個人受任を認めている会社はほとんどないのではないかと思っています。)。そのため、個人的には、街弁として働くことにも大きな魅力があると思っており、福利厚生を手厚くする、勤務形態を柔軟に変更する(在宅ワークを積極的に導入する)といった対応をとることにより、街弁業務の人気を少しは復活できるのではないかと思っています。
しかし、いかんともし難いのは、弁護士の都市部集中(新人の都会志向)でしょう。ここ数年、弁護士の求人を出している側として感じるのは、東京や大阪といった都市部にある事務所(本店、支店)への応募は一定数あるものの、それ以外の場所(当事務所でいえば、熊本、仙台)への応募は大変少なく、都市部以外での採用は本当に厳しいということです。この点について、弁護士数が少ないエリアで働いた方が、弁護士数が過剰な都市部で働く場合と比較して、法律相談センターの法律相談に入れる頻度や国選の割り当て数が多くなるので、必然的に個人受任事件の件数も増えますし(収入を増やせますし)、家賃や駐車場代も安価なので、余暇に費やすお金を確保しやすいはずですが、そういった点は事務所選択にあたってあまり重視されていないようです。ほかにも、都市部以外のエリア(弁護士数が少ないエリア)においては、委員会活動等を通じて他の弁護士とのつながりを強く持ちやすいので、先輩弁護士から手厚い指導を受ける機会に恵まれていますし、都市部のように弁護士業務が細分化されていませんので(専門型、ブティック型の事務所は少ないので)、いろいろな事件を担当する機会が豊富にあるというメリットもあるはずですが、これらの点もあまり重視されないようです。
私も昔は都会に強くあこがれて一橋大学に進学したので(東大は私にとってハードルが高かったのです…)、あれこれと偉そうにいうことはできませんが、確かに、若い頃って漠然と都会にあこがれてしまうんですよね…。特に、弁護士の場合、年数を重ねていくことで人とのつながりや顧客が増えていきますので、簡単に事務所移転できない(転勤できない)という事情もあると思います。そのため、最初の事務所選びにあたっては、どの都道府県にある事務所の中から選ぶのかという点は重要であり、規模の大きな都市を魅力に感じて志望する人は多いと思います。転勤があるという条件では、新人弁護士の確保はさらに難しくなるのが実情です。
本題に戻りますが、80期あたりから買い手市場になるのではという予想の背景には、AIの進化による業務の変化(生産性の向上)や期日のウェブ化の普及による効率化といった事情があるようです。
確かに、期日のウェブ化は現時点においてもかなり普及していて、出廷する手間が不要になった分、時間を確保しやすくなりました。また、このようにウェブ化が普及していければ、東京都内にあっても、札幌や長崎といった遠方のエリアの事件も担当しやすくなり、各エリアに支店を設ける必要性は低下しつつあるのではと思います。
しかし、街弁業務に限っていえば、AIによる業務の代替性は高くなく、AIが普及しても需要は減少しないのではないかと思っています。契約書の作成等についてはAIの進化によって、弁護士に依頼する必要性は減少していくと思いますが、個人間の紛争解決をAIで代替することはできないと思います。人は合理性のみで意思決定をするものではなく、感情が意思決定に大きく影響しますので、どれほどAIが普及しても、代理人弁護士を立てて交渉することの必要性はなくならないというのが私の考えです。
ということで、街弁業務については、今後も売り手市場が続くのではないかと思っていますが、企業内弁護士や企業法務分野における弁護士需要が低下し、それらの弁護士求人数が低下することの反射的効果として、街弁事務所への応募が増えて売り手市場が徐々に解消する可能性はあるかもしれません。
ちなみに、私は61期ですが、その当時はすさまじい買い手市場でした。当時、故郷である京都市内での就職を希望していたのですが、公に弁護士求人を出していた事務所はほぼなかったため、京都市内での就職は諦めて、比較的たくさんの求人が出ていた東京都内で勤務先を探し、なんとか採用してもらって今に至っています。京都市内の事務所に入所できていたら、今頃どうなっていたんだろうとふと思ったりしますが、「人間万事塞翁が馬」ということわざのとおり、結果として楽しい日々を過ごせていますので、人生わからないものですね。
タグ
2025年9月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記