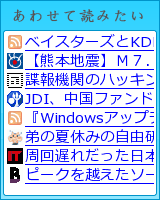ロースクール入試、公務員試験対策(行政法論文)
今回は、ロースクール入試、公務員試験対策、さらには司法試験対策としてオススメの行政法の基本書、演習書等を紹介したいと思います。
あらゆる試験に幅広く対応できる基本書は、櫻井先生、橋本先生が執筆されている「行政法」(弘文堂)で決まりでしょう。文体が平易で分かりやすく独学にもピッタリです。これと、判例集、あとから紹介する演習書でほぼ対応できると言っても過言ではありません。他には、一冊で総論、救済法を網羅するものとして原田尚彦先生の「行政法要論」(学陽書房)も定番で外せないですね。櫻井先生、橋本先生執筆の上記基本書に比べると全体的に表現はカタいですけど。
個人的には、どちらか選ぶなら、櫻井先生、橋本先生の本を選びます。
で、上記の本で物足りないと考える人は、塩野宏先生の「行政法I」、「行政法Ⅱ」(有斐閣)、芝池先生の「行政法総論講義」、「行政救済法講義」(有斐閣)、宇賀克也先生の「行政法概説」(有斐閣)あたりから選ぶことになると思いますが、僕のイチオシは芝池先生の基本書ですね。どれを選んでも大差ないですが、塩野先生の本は文体が格調高く、じっくり腰を据えてやる人以外には向かないかなと。あとは、宇賀克也先生の基本書よりも芝池先生の基本書の方が理論的な説明は厚くなされてるように思います。
なお、司法試験受験生以外なら、一冊にまとまってる基本書を選んで何度も読み返し、全体像をイメージできれば十分です。
演習書については、日本評論社から出てる「事例研究 行政法」第2版がベストです。他の演習書よりも解説がダントツで分かりやすいですね。これに比べて、「行政法 事案解析の作法」(日本評論社)は解説が細かくて、読みにくく感じますし、同じく日本評論社から出てる「ケースメソッド公法」(憲法も含まれています)は、最終的な結論がはっきり記載されてない箇所が多くて歯痒い感じです。あと、月刊「法学教室」(有斐閣)掲載の演習もけっこう使えます。
ロースクール、公務員受験生だと、国家総合職狙いの人はアレコレと手を広げずに「事例研究 行政法」だけやれば十分です。
タグ
2011年11月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
刑法の基本書~司法試験対策、公務員試験対策~
久々に資格試験受験生向けにオススメ基本書を紹介したいと思います。あくまで私の独断ですが‥。
まず、国家公務員総合職(国家I種)試験であれば、刑法は択一試験しかありませんので、刑法の勉強に時間をかけるのは得策ではありません。そこで、1冊で通説、判例の立場を概観出来る基本書がいいと思います。やや古いですが、刑法の大御所である大塚仁先生の「刑法入門」(有斐閣)が分かりやすくてよいですね。増刷の度にこまめに補訂されてますし。あとは、山口厚先生の「刑法」(有斐閣)も1冊でよくまとまっています。でも、山口先生の本は、大塚先生の本よりも難しく、語り口調ではないので、独学でマスターするのはやや難しいかもしれません。また、分量も大塚先生の本よりも100ページ以上多いので、通読には時間がかかります。公務員試験の択一対策はとにかく早く、一気にインプットを完了した上で過去問を解くのが効果的ですので、薄めの本を選ぶのがいいです。もちろん予備校に通っている人はその予備校のテキストをおさえておけばインプットは足りると思います。
次に司法試験対策、法科大学院入試対策ですが、上記の基本書ではインプットが足りません。ここは、刑法総論、刑法各論の2分冊を使わざるを得ないでしょう。いわゆる行為無価値、結果無価値で大きく分かれますが、どちらの立場に立ってもいいでしょう。行為無価値の人は、刑法総論は「刑法総論講義案」(司法協会)が一番無難だと思います。学者の先生方からは、理論的な甘さを批判されることが多い本ですが、司法試験の事例問題を解くにあたって差がつくようなものではないでしょう。各論は、川端博先生の「刑法各論講義」(成文堂)が詳しくて理論的にも分かりやすく、オススメします。なお、川端博先生の「刑法講義総論」(成文堂)もあり、こちらも総論の教科書の中では悪くないと思います。個人的には、行為無価値であれば、斎藤信治先生の「刑法総論」、「刑法各論」(有斐閣)が面白くて大好きです。「社会心理的衝撃性」という新たな概念を用いておられ、ちょっと通説と異なる立場ですけどね。他には、井田良先生の基本書が最近人気みたいですが、こちらは通読していないので、何とも言えません。
結果無価値の人は、山口厚先生の「刑法総論」、「刑法各論」(有斐閣)を外せないのではないでしょうか。ただ、刑法総論はかなり難しく感じると思います。あと、松宮孝明先生の「刑法総論講義」、「刑法各論講義」(成文堂)も難解ですが、読んでいて面白いですね。しかし、司法試験向きとは言えないかもしれませんが。残すは、最近メジャーな西田典之先生の「刑法総論」、「刑法各論」(弘文堂)となるんでしょうが、実は私、この本を通読していないので何とも言えません。というわけで、結果無価値の基本書では、これといった決め手をご紹介することが今のところできません。ごめんなさい_| ̄|○
行為無価値であろうが、結果無価値であろうが、論文対策が重要なのは間違いなく、どの学説に立ったからといって点差が出るようなことはないと思います。ロースクールの先生の学説に近い本を選んでおけば間違いないし、混乱もしないのではと思います。
注意すべきは、いろんな基本書をつまみ食い的に利用することですね。これはタブーです。刑法(特に総論)は論理的思考が最も問われる法律科目ですので、一貫した記述をすることが必要です。いろんな学説をごちゃ混ぜにしないよう気をつけましょう。
タグ
2011年11月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
民法のオススメ本
久々に司法試験、国家公務員試験受験生向けに民法のオススメ基本書を紹介します。あくまで私の独断ですが。
今のところ、最メジャーなのは、いわゆる内田民法シリーズでしょう。僕が受験生のときから大人気で、判例の事案ベースの事例を引用しながら書いてあって、まさに教科書という感じです。ですが、個人的には好きになれませんでした。論文書くときに、論証へ転化しにくい感があって…。
で、そんな私は受験生時に、新世社から出てる平野裕之先生の「基礎コース民法」をけっこう使ってましたね。某掲示板で、この本が一時的にもてはやされてました。でも、実はこの本は読みにくいです。内容よりも筆者の文章に慣れるまでに時間かかりますので、ちょっとオススメできません。分量は適度で、内容はいいんですけど。
そんな私の現時点でのイチオシは、単一著者シリーズなら川井健先生の民法概論シリーズです。我妻先生のお弟子さんで、オーソドックスな学説を展開されてます。文章も単調ですが、読みやすいです。公務員受験生にとっては、やや細かすぎるかもしれませんけど。
他にも近江先生の民法講義シリーズ(成文堂)とか大村先生の基本民法シリーズ(有斐閣)などたくさんありますが、通読してないので、評価できず。
まぁ、民法も他の科目と同様に知識を入れたら、ひたすら問題演習するのが重要ですね。そういうことで、基本書は自分にあったものであれば何でもいいと思います。こういうと、元も子もないですけど(笑)
なお、上記の紹介はあくまで単一著者によるシリーズ物(完結しているものに限る)に限定しています。優れた基本書はたくさんありますが、全て読んでませんし、紹介する余裕がないんで。またの機会に、分野ごとで紹介できればと思います(^_^)
タグ
2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
資格試験、公務員試験の勉強法(続き)
先日、資格試験等の勉強法について私なりに思うところを書きました(前回の記事:資格試験、公務員試験等の勉強法)。勉強法といっても、人それぞれ置かれている状況が違いますし、性格も異なるわけですので、僕のオススメする勉強法が万人にうけるとは思ってません。
でも、やっぱり多くの人にとって役に立つんじゃないかとも思ったり‥。
今日は、前回の記事にちょっと補足しておきたいと思います。
資格試験、公務員試験は択一式(多肢選択式)と論文式があります。このうち択一式試験に合格するには、択一過去問をひたすら繰り返して正答率をあげることで大丈夫であることは前回の通りです。ほかに必要なことは、本番さながらの実践感覚を養うために予備校の模擬試験を何度か受験すればよいと思います。強制的に時間内で解くことになる点で模試は有用でしょう。ただし、模擬試験はオリジナルな問題を組み込みますので、時折マニアックな問題が含まれてます。そういう問題については、間違えても気にしないことが必要です。せっかく模試を受けたわけですから、復習くらいはすべきでしょうけど。ほかには、法律択一試験であれば、最新判例をチェックすれば十分かと。
他方で論文式試験、とりわけ法律論文試験については、過去問と同じテキストをひたすら繰り返すことが効果的であることは前回の通りですが、注意しないといけないのは、ダラダラとやらないことです。論文式試験では、真っ白な答案に一から書き起こしていくわけですから、暗記のレベルは、見て思い出せば足りるレベルの択一式とは異なり、正確に書けるレベルじゃないといけません。でも、法律は覚えるべき分量が膨大で、テキストを一周する頃には最初にやったことを忘れてるなんてことがよくあります。これをできるだけ防いで、知識を確実に暗記するには、テキストの回転速度をひたすら上げるのがいいかと思います。1ヶ月で同じテキストをみっちり1回やるよりは、3回ざっくりと繰り返す方が知識は定着するはずです。
それから、テキストを読むときには、常に論文で出題されたら、どう書くかという点を意識することが大事だと思います。この読み方だと読むスピードはダウンしますが、繰り返せば次第に速度はあがります。
以上、接見に向かう途中の電車内で書いてみました。読み返してみると、昔の自分に言い聞かせているようで、若干恥ずかしくなってきますね(; ̄O ̄)私、受験生時にはいろんなテキストを読みあさって、いろんな問題を解いてみて、結局わかった気になってただけでしたから‥。不確実な知識しか身についておらず、論文式試験どころか、択一式試験でも大苦戦でした。
タグ
2011年9月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
憲法
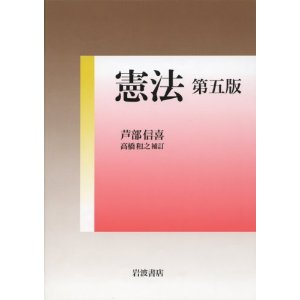 実務についてからはほとんど憲法、行政法をやる機会がない。
実務についてからはほとんど憲法、行政法をやる機会がない。
でも、僕は時折り、憲法の基本書を読み直してます。
司法試験に受かってから、それまで読んだことがない本にも何冊か目を通したけど、ダントツ分かりやすくてオススメなのは、芦部先生の「憲法」(岩波書店)ですね。これは、長年、多くの人の間で読み継がれているだけのことはあります。司法試験、国家公務員試験、地方公務員試験を問わず、マスターすべきです。
松井先生の「日本国憲法」(有斐閣)も分かりやすいんですが、プロセス的憲法観に立たれていて、少数説であることを念頭において読むのがいいです。
ちなみに、最近、成文堂から発売された佐藤幸治先生の「日本国憲法論」は、噂通り、表現の難しい記載がいくつかあり、初学者は避けた方が無難ですね。
あえて芦部憲法のサブテキストとして勧めるなら、有斐閣アルマの憲法ですかね。けっこう丁寧な内容で、もっと売れてもいい気がします。
有斐閣
売り上げランキング: 90456
有斐閣
売り上げランキング: 88305
タグ
2011年9月11日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法律学
究めるのは難しい。
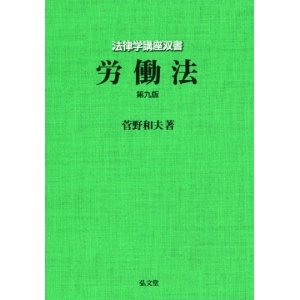 今日は、労働法を人に教える機会があって、基本書を見直しました。
今日は、労働法を人に教える機会があって、基本書を見直しました。
弁護士として、労働事件に携わるようになって早2年が過ぎようとしていて、労働法についてはある程度自信がついてきたところだったけど、ここにきて労働法の理解が甘いことに気づかされた。
普段からこまめに知識補充することが大事だなと。仕事中はもっぱら書面作成ばかりで時間が取れず、空いた時間を上手く利用して、今後もこまめに勉強せねば(~_~;)法律を究めるのに王道はなく、先は長いです。
ちなみに、労働法の基本書といえば、実務家として菅野和夫先生の本は外せない。でも、個人的には、水町先生の労働法が読んでいて面白く感じる。司法試験の受験生なら、水町勇一郎先生の本と判例集、演習書で司法試験に十分対応できると思う。国家公務員総合職試験の受験生なら、択一問題しか出ないから、有斐閣から発刊されているアルマ労働法が比較的コンパクトにまとまっていて丁度よいかと。もしくは、信山社のプラクティス労働法もよいですね。
企業の法務部勤務の方は、菅野先生の労働法は必須で、あとはお好み次第ですかね。
今後もいい本、新刊本などがあれば紹介していきます。
有斐閣
売り上げランキング: 321021
信山社
売り上げランキング: 460918
タグ
2011年9月1日 | コメント/トラックバック(0) |